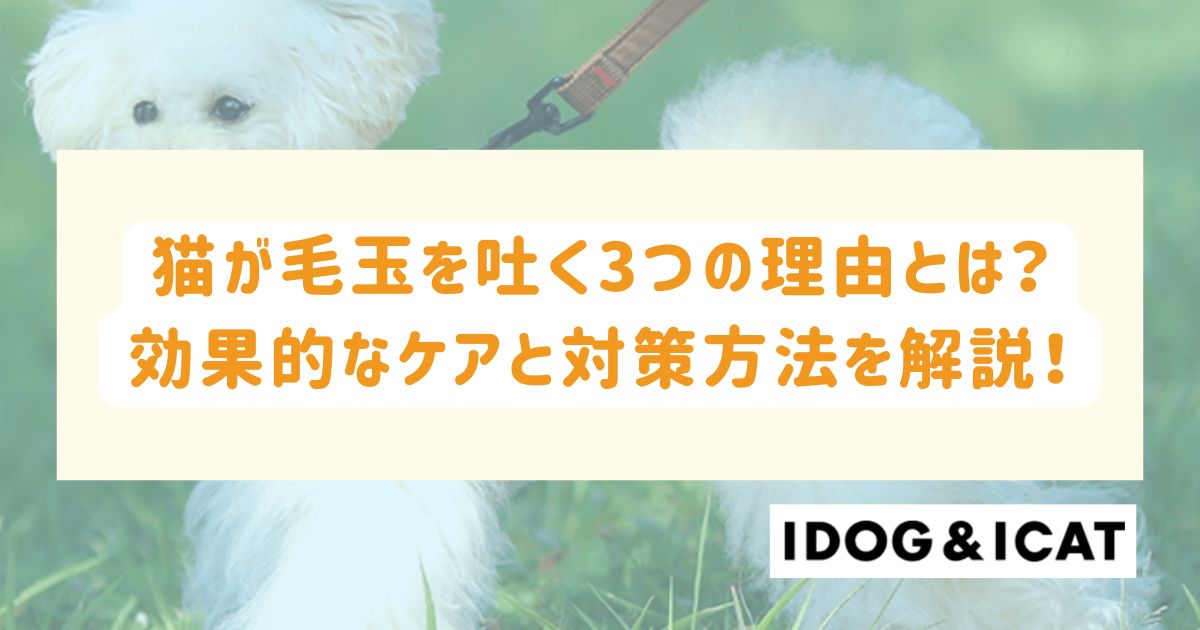猫の毛玉に関して、具体的に以下のような疑問を感じたことはありませんか?
- 猫が毛玉の塊を吐いたらどうしたらいい?
- 猫が毛玉を吐く原因は?
- 猫が毛玉を吐くのはストレスが原因?
実は、猫の毛玉対策はブラッシングや食事管理だけでなく、猫の体調や生活環境にも関わっているのです。
そこで本記事では、毛玉を吐く原因や対策、さらに猫の健康に悪影響を及ぼさないためのケア方法について網羅的に解説します。
愛猫のために少しでも気になる方は、ぜひ最後までご覧くださいね!
猫が毛玉を吐く3つの理由

猫が毛玉を吐くのは、自然な生理現象です。
しかし、その理由をしっかり理解している人は少ないかもしれません。
猫が毛玉を吐く主な原因は、以下の3つです。
- 毛づくろいの習慣
- 毛の消化器官での動き
- 毛玉を吐く必要性
毛づくろいの習慣
猫は1日の多くを毛づくろいに使います。
この行動は、体を清潔に保つだけでなく、健康のためにも重要です。
しかし、猫が毛づくろいをするとき、舌で自分の毛をたくさん飲み込んでしまうことがあります。
特に長毛種の猫や、季節の変わり目で毛が大量に抜ける換毛期には、飲み込む毛の量が増え、毛玉ができやすくなります。
例えば、ペルシャ猫のような長毛種は、毛づくろいによって通常より多くの毛を飲み込んでしまうため、毛玉が頻繁にできる傾向があります。
毛の消化器官での動き
通常、猫が飲み込んだ毛は、消化器官を通って自然に体外に排出されます。
しかし、飲み込んだ毛が多すぎたり、消化器官がうまく働かない場合、毛が胃の中で溜まり、固まり(毛玉)を作ることがあります。
この毛玉が大きくなりすぎると、腸を通過できず、猫は本能的にそれを嘔吐しようとします。
例として、消化がスムーズにいかないと、毛が胃に滞留して大きな毛玉になり、猫が吐く回数が増えることがあります。
毛玉を吐く必要性
猫が毛玉を吐くのは、体内に溜まった毛を排出するための自然な防衛メカニズムです。
もし毛玉が大きくなりすぎると、腸が詰まるなど消化管に重大な問題を引き起こす可能性があります。
そうした状態は非常に危険で、早急な治療が必要になることもあります。
ただし、頻繁に毛玉を吐く場合や、吐くときに他の異常(苦しそうな様子など)が見られる場合は、すぐに獣医師に相談することが重要です。
正常な毛玉を吐く頻度と様子

猫が毛玉を吐くのは、人間が髪を整えるように、体の自然な手入れの一環です。
ただし、猫がどの程度毛玉を吐くのが正常か、またその頻度を理解することが、健康状態を見極めるためには大切です。
健康な猫が毛玉を吐く頻度
一般的に、健康な猫は「1週間に1〜2回ほど」毛玉を吐きます。
ただし、猫の品種や個体によって、その頻度は異なるのです。
例えば、長毛種の猫は短毛種よりも頻繁に毛玉を吐く傾向があります。
具体例として、ペルシャ猫やメインクーンのような長毛種は、毛が多いため、毛づくろいの量も増え、結果として毛玉を吐く回数が多くなりがちです。
参考:ペルシャは猫の王様!その性格や特徴は?チンチラとの違いも解説! #138
季節や換毛期の影響
一般的に、猫の毛が生え変わる春や秋の換毛期は、毛が大量に抜けるため、猫が毛玉を吐く回数も増えます。
この時期は、「ブラッシングの頻度を増やす」などして、毛玉ができないようにケアすることが大切です。
また、毛玉ケア用のフードを与えるのも有効な手段です。
室内飼いと外飼いの猫の違い
室内飼いの猫は、外で飼っている猫よりも毛玉を吐く頻度が高くなる傾向があります。
これは、室内猫は運動量が少ないため、消化機能がやや弱くなることが原因の一つです。
また、退屈しのぎに毛づくろいを過剰に行うことも、毛玉の形成に関係しています。
一方で、外で飼われている猫は、運動量が多く、消化器の動きが活発になるため、毛玉を吐く頻度が比較的少ない傾向があります。
ただし、そもそも外飼いの猫は怪我や病気のリスクが高くなるため、室内で飼育することが推奨されています。
参考:猫を飼うなら室内と放し飼いどちらがいいの?放し飼いがNGな5つの理由 #153
注意が必要な毛玉の吐き方

猫が毛玉を吐くこと自体は自然な行動ですが、その頻度や様子によっては、健康に問題がある可能性があります。
特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 急に吐く頻度が増えた
- 吐くときに異常が見られる
- 毛玉以外の異物が混じっている
急に吐く頻度が増えた
猫が急に毛玉を吐く回数が増えた場合、何らかの異常が隠れていることが考えられます。
その1つは、ストレスや不安です。
ストレスを感じていると、猫は過剰に毛づくろいをすることがあります。
例えば、引っ越し、新しい家族の登場、家のレイアウトの変更などがこれに該当します。
このように生活環境に大きな変化があると、ストレスを感じて毛づくろいの回数が増えることがあります。
また、皮膚のかゆみや寄生虫によっても、猫が頻繁に毛づくろいを行い、結果として毛玉を吐く回数が増えることもあるのです。
さらに、胃腸の不調が原因で、飲み込んだ毛が消化されずに体内にたまることで、毛玉を吐く頻度が高くなることもあります。
吐くときに異常が見られる
猫が毛玉を吐く際の様子にも気をつけることが重要です。
通常、猫は毛玉を吐く前にのどを鳴らしたり、首を伸ばす動作を見せますが、次のような異常が見られたら注意が必要です。
- 吐くときに苦しそうにしている
- 吐いた後、元気がなく、食欲も落ちている
- 吐いた後もむせ続けている
- 吐きたくても吐けない(空嘔吐)
これらの症状は、毛玉が食道や胃に詰まっている可能性を示しています。
この状態は危険であり、すぐに獣医師の診察が必要です。
毛玉以外の異物が混じっている
毛玉を吐いた際、毛玉以外の異物が混じっている場合は、さらに注意が必要です。
もし以下のようなものが含まれていたら、早めに獣医師に相談しましょう。
- 血液や粘液
- 植物の葉や茎
- プラスチックや紐などの人工物
- 虫や寄生虫
特に血液が混じっている場合、消化器官にダメージを受けている可能性があります。
また、プラスチックや紐などの人工物が含まれている場合、猫が誤って危険な物を飲み込んでしまった可能性があります。
日頃から猫の行動や体調をよく観察し、異常が見られたらすぐに獣医師に相談することが、猫の健康を守るためには非常に重要です。
猫が毛玉を吐く季節や環境

猫が毛玉を吐く頻度や量は、季節や生活環境に大きく影響されます。
特に季節ごとの毛の生え変わりや、換毛期に注意が必要です。
季節ごとの毛の生え変わり
猫の毛は、季節の変わり目に生え変わります。
春には冬毛が抜けて夏毛に、秋には夏毛が抜けて冬毛へと変わります。
この時期、猫は普段よりも多くの毛を飲み込むことになります。
特に春と秋の換毛期は、毛玉を吐く回数が増える傾向があります。
抜け毛が大量に発生するため、猫が毛づくろいをする際に、毛をたくさん飲み込んでしまいやすいのです。
換毛期のケア方法
換毛期には、日常のケアを強化することで、毛玉の形成を抑えられます。
以下の方法で、猫の体をきれいに保ち、毛玉の発生を防ぎましょう。
- ブラッシングの頻度を増やす
- 専用コームを使う
- バスタオルでケア
- 毛玉ケア用フードを与える
猫の毛を取り除くために、「毎日1〜2回のブラッシング」が効果的です。
毛が体内にたまるのを防ぐために、こまめに行いましょう。
また、換毛期には、通常のブラシに加えて、毛玉防止用の専用コームを使うことで、毛をより効果的に取り除けます。
長毛種の猫には特に効果的です。
バスタオルの活用も有効です。
猫を優しく包み、軽く撫でてあげると、抜け毛を取り除きやすくなります。
これにより、飲み込む毛の量を減らせます。
上記に加えて、「毛玉ケア用フード」も存在しているので、こちらを活用してみるのも1つの手段です。
猫の毛玉対策【予防と日常のケア方法】

猫の健康を守るために、毛玉の予防は日々のケアとして欠かせません。
特に、以下の3つのポイントを押さえておくことで、毛玉ができにくい環境を作り、猫の健康を維持することができます。
- 正しいブラッシング
- 毛玉対策用の食事
- その他の予防策(水分補給や生活環境の整備)
正しいブラッシング
ブラッシングは毛玉を防ぐための基本的なケアです。
正しい方法でブラッシングを行うことで、毛玉の発生を大幅に減らせられます。
ブラッシングの頻度とタイミング
猫の毛の長さや季節に応じて、ブラッシングの頻度は変わります。
以下を目安にしてください。
- 短毛種:週に2〜3回
- 長毛種:毎日
- 換毛期:1日2回が理想的
タイミングとしては、猫がリラックスしているときが好ましいです。
例えば、食後や夜に落ち着いた時間帯などが挙げられます。
また、猫が自分で毛づくろいを始めたタイミングでブラッシングをすると、より効果的に毛を取り除けます。
猫に合ったブラシの選び方
猫の毛の長さや質感に合わせて、適切なブラシを選ぶことが大切です。
- 短毛種:ゴムブラシや柔らかい毛のブラシが適している。
- 長毛種:ピンブラシやコームが効果的。
- 下毛の多い猫:ファーミネーターなど、抜け毛を効果的に取り除けるツールが便利。
季節や猫の毛の状態に応じて、複数のブラシを使い分けると、より効果的なケアが可能です。
ブラッシング時の注意点
ブラッシングを行う際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 毛の流れに沿って優しくブラッシングする
- 皮膚や毛の状態を観察する
無理に力を入れると猫に痛みを与える可能性があるため、ゆっくり丁寧に行うことが大切です。
ブラッシング中に異常(赤みやかゆみ、抜け毛の異常など)があれば、早めに獣医師に相談しましょう。
このように、定期的にブラッシングを行うことで、毛玉の形成を効果的に防げます。
毛玉対策用の食事
食事も毛玉対策の重要なポイントです。
毛玉ケア用のフードを日常的に与えることで、体内で毛が固まりにくくなり、自然な毛玉排出を促せます。
毛玉ケアフードに含まれる成分
毛玉ケアフードには、毛玉の形成を防ぐために次のような成分が含まれています。
- 食物繊維:毛の排出を促進し、体内に毛がたまりにくくなる。
- オメガ3脂肪酸:皮膚や被毛を健康に保ち、毛が抜けにくくなる。
- ビタミンE:抗酸化作用により、毛の健康をサポートに役立つ。
- タウリン:毛の成長に必要な栄養素で、毛の質を維持する。
これらの成分を含むフードを与えることで、猫の体内での毛玉の形成を予防できます。
その他の予防策(水分補給や生活環境の整備)
ブラッシングや食事以外にも、いくつかの対策を取り入れることで、毛玉予防がさらに効果的になります。
水分摂取の促進
猫が十分な水分を摂ることで、消化機能が向上し、毛が体外に排出されやすくなります。
次の方法を試して、水分摂取を促しましょう。
- 新鮮な水を常に用意する
- 猫専用のウォーターファウンテンを設置する
- ウェットフードを取り入れる
水はこまめに取り替え、清潔な状態を保つことが大切です。
ウォーターファウンテンによって流れる水は、猫にとって魅力的で、自然に水を飲む量が増えることが期待できます。
また、水分の多いウェットフードを与えることで、食事からも水分を摂取させることが可能です。
参考:【子猫が水を飲まない!】今すぐできる5つの対処法とは?1日に必要な水分量も解説 #124
猫草の活用
猫草は、猫が自分で毛を吐き出すために役立ちます。
猫草を使用する際には、次のポイントに注意してください。
- 安全な猫草を用意する
- 定期的に交換する
- 食べ過ぎに注意する
飼育環境の整備
猫が毛玉を作りにくい環境を整えることも、毛玉予防には効果的です。
以下のポイントを参考に環境を整えましょう。
- 毛が絡まりにくい家具やカーペットを選ぶ
- こまめに掃除をする
- 静電気を防ぐために湿度を保つ
- 猫のストレスを軽減する
長毛種の猫がいる場合、毛が絡みにくい素材の家具やカーペットを選択しましょう。
抜け毛が部屋にたまると、猫が再度飲み込んでしまう可能性があります。
そのため、掃除を定期的に行い、清潔な環境を維持することが重要です。
また、乾燥すると毛が絡まりやすくなるため、適度な湿度を保つことで静電気を防げます。
運動不足はストレスになり、過剰な毛づくろいにつながります。
そのため、十分な遊び道具や運動スペースを用意してあげましょう。
猫のストレスを軽減できます。
参考:【危険】飼い猫が運動不足かも!遊ばない猫を動かす5つのコツとは? #120
これらの対策を日常に取り入れることで、猫の毛玉の形成を効果的に防ぎ、健康を保つことができます。