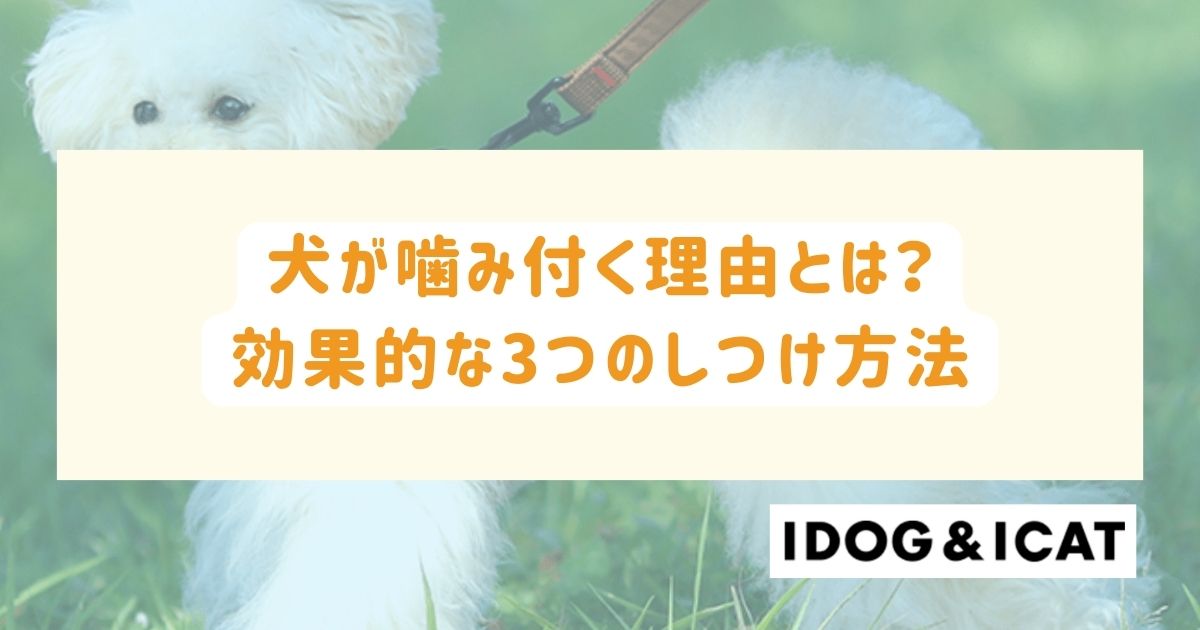犬が噛み付く理由

犬が人や他の動物に噛み付く理由は様々ありますが、大きく分けると本能的な行動、飼育環境やトレーニング不足、犬種ごとの性格が挙げられます。
本能的な行動
犬が本能的に噛み付く理由には、恐怖心と防衛本能、そして痛みや不快感があります。
恐怖心・防衛本能
犬は知らない人や動物、突然の大きな音や振動に対して警戒心を持ち、自分の身を守るために噛み付くことがあります。
痛み・不快感
怪我や病気、発情期などによる痛みや、不快な触り方や扱い方をされた際に、犬は噛み付くことがあります。
飼育環境やトレーニング不足
犬の噛み付きは、飼育環境やトレーニング不足が原因となることもあります。
十分な運動や遊びの機会不足
犬がエネルギーを溜め込むと、攻撃的な行動に繋がる可能性があります。
社会化不足
他の犬や人との接点が少ない、適切な社会化トレーニングを受けていない犬は、噛み付きトラブルを起こしやすくなります。
誤ったしつけ
叩いたり怒鳴ったりするなど、犬を恐怖させるようなしつけ方法は、噛み付きを引き起こす可能性があります。
犬種ごとの性格
犬種によって性格が異なり、噛み付きの傾向も変わってきます。
もともと警戒心や防衛本能が強い犬種
ジャーマン・シェパードやドーベルマンなどは、警戒心が強く、適切なしつけがされていないと噛み付きを起こしやすくなります。
興奮しやすい性格の犬
チワワやミニチュアダックスフントなどの小型犬は、興奮しやすい性格を持っているため、噛み付きに注意が必要です。
※あくまで犬種による傾向で、性格は個体差が大きい。
総体的に犬が噛み付く理由を理解することは、噛み付き事故を防ぐ上で非常に重要です。
飼い主は自分の愛犬の性格や行動をよく観察し、適切な飼育環境としつけを行うことで、犬の噛み付きを防ぐことができます。
犬が「飼い主に」噛み付く理由

犬が飼い主に噛み付く理由は、様々な要因が複雑に絡み合っています。
恐怖心やストレス
まず、過去に飼い主から物理的な罰を受けた経験から、犬が飼い主に対して恐怖心を抱いていることがあります。
また、引っ越しや新しいペットの導入などの環境の変化によるストレスから、犬が攻撃的になることもあるでしょう。
参考:犬と引越ししたい!よくある7つのトラブルと対処法とは?
痛み・不快感
痛みや不快感も、犬が飼い主に噛み付く原因となり得ます。
怪我や病気による痛みで触れられることに敏感になったり、皮膚の炎症やアレルギーによる痒みから不快感を感じたりすることで、犬は攻撃的になることがあります。
不適切なしつけ・社会化不足
不適切なしつけや社会化不足も見逃せない要因です。
子犬の時期に噛み癖に対する適切なしつけを受けていなかったり、人との適切な関わり方を学ぶ機会が不足していたりすると、犬は飼い主に対して攻撃的な行動をとってしまうことがあります。
優位性の表示
優位性の表示も、犬が飼い主に噛み付く理由の一つです。
犬が自分を「リーダー(ボス)」だと思い込み、その地位を守るために飼い主に威嚇的な行動をとったり、食事やおもちゃを独占するために攻撃的になったりすることがあります。
そもそもこのような関係は良くありません。
犬が自分を「リーダー(ボス)」だと思い込んでしまう原因は、主に飼い主との関係性に問題があるためです。
例えば、飼い主が犬に対して曖昧な態度を取ったり、一貫性のないしつけを行ったりすることで、犬は自分が家庭内の上位者であると認識してしまうことがあります。
そして主従関係が逆転してしまうと、噛み付くトラブルだけでなく、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 飼い主の指示に従わなくなる
- 吠えやすくなったり、攻撃的になったりする
- 他の人や犬に対して過剰に縄張り意識を持つ
- 飼い主との遊びや触れ合いを避けるようになる
- 家の中で好き勝手に行動するようになる
過剰な遊びや興奮
遊びの最中の興奮が高まり、噛むことでその興奮を発散しようとすることもあります。
飼い主が不用意に犬の興奮を煽ってしまい、コントロールを失ってしまうこともあるでしょう。
これらの理由を理解した上で、飼い主は犬との信頼関係を築き、適切なしつけやコミュニケーションを心がける必要があります。
犬が飼い主を噛むという行動は、犬からの何らかのサインであると捉え、その根本的な原因を取り除くことが重要です。
子犬が噛む理由

子犬が噛む理由は、成犬とは異なり、発育段階に関連した要因が大きく影響しています。
歯の生え変わりによる不快感
子犬は、生後2〜8ヶ月頃に乳歯から永久歯へと歯が生え変わる時期を迎えます。
この間、歯茎の痒みやむずがゆさから、噛む行動を示すことがあります。
子犬が身近にあるものを何でも噛んでしまうのは、この不快感を和らげようとする自然な行動なのです。
遊びの一環としての噛み行動
子犬にとって、噛むことは遊びの重要な要素の一つです。
子犬同士の遊びでは、互いに噛み合いながらコミュニケーションを取り、社会性を育んでいきます。
また、飼い主との遊びの中でも、子犬は手や足を噛んで興奮を表現することがあります。
世界の探索と学習
子犬は、生まれてから約8週間までの社会化期に、口を使って世界を探索し、学習していきます。
新しいものを口に入れて噛むことで、その感触や味、匂いを確かめ、自分の周りの環境を理解しようとします。
この時期の噛み行動は、子犬の成長過程において重要な役割を果たしているのです。
しつけの必要性
子犬の噛み行動は、自然な発達過程の一部ではありますが、放置すると問題行動へと発展してしまう可能性があります。
そのため、飼い主は子犬の噛み行動を適切にコントロールし、正しい行動を教えていくことが重要です。
具体的には、噛まれたら「痛い!」と声を上げて遊びを中断し、代わりに噛んでも良いおもちゃを与えるなどの対応が効果的です。
また、子犬が人の手や足を噛まないように、積極的に社会化トレーニングを行い、適切な遊び方を教えることも大切です。
参考:子犬の噛み癖がひどいときはどうしたらいい?改善する3つのポイント
犬が噛みつく際に生じる被害

犬に噛まれた際には、身体的な被害だけでなく、精神的な被害も生じる可能性があります。
また、犬の噛む力は非常に強く、重大な怪我につながる恐れがあります。
身体的な被害
犬に噛まれた場合、以下のような身体的な被害が考えられます。
皮膚の傷、打撲、出血
犬の歯は鋭く、噛みつかれた部位には皮膚の傷、打撲、出血などが生じます。
傷の深さや大きさは、犬の大きさや噛みつきの強さによって異なります。
感染症のリスク
犬の口内には多くの細菌が存在するため、噛み傷から感染症を引き起こす可能性があります。
代表的な感染症として、破傷風や狂犬病などが挙げられます。
「破傷風」とは、筋肉の硬直や呼吸困難を引き起こし、重症化すると命に関わる危険な病気です。
一方、「狂犬病」は、初期症状として発熱や倦怠感が現れ、後期には恐水症状や興奮、麻痺などの神経症状が見られます。
発症すると、ほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。予防には、狂犬病ワクチンの接種が不可欠です。
犬に噛まれてしまった場合は、まず傷口を石鹸で十分に洗浄し、速やかに医療機関を受診しましょう。
飼い主は、愛犬の健康管理とワクチン接種を適切に行い、他者への感染リスクを最小限に抑えることが求められます。
精神的な被害
犬に噛まれた経験は、被害者と犬の両方に精神的な影響を与えます。
被害者側の恐怖心やトラウマ
犬に噛まれた被害者は、恐怖心やトラウマを抱えることがあります。
特に子供や高齢者は、精神的な影響を受けやすい傾向にあるので、特に注意が必要です。
例えば、子供が犬に噛まれた後、公園や道端で犬を見かけるたびに怯えてしまい、一人で外出することができなくなることもあります。
犬側の不安やストレス
反対に噛みつきを起こした犬も、問題行動として扱われることで不安やストレスを抱えることがあります。
飼い主との関係性が悪化したり、ひどいケースでは飼育放棄や処分につながるケースもあるのです。
具体的には以下のようなケースがあります。
- 飼い主が犬の噛みつき行為に対して過剰に怒るようになり、犬が飼い主を恐れるようになる。
- 犬はそのストレスから、過剰に吠えたり、排泄のコントロールができなくなったりする。
犬の噛む力【豆知識】
犬の噛む力は、犬種や個体差によって異なりますが、非常に強力です。
大型犬の場合、約200〜400psiの噛む力を持っていると言われています。
これは、人間の噛む力の約4〜5倍に相当します。
このように犬に噛まれた際の被害は、身体的・精神的な面で深刻な影響を及ぼします。
犬の噛みつきトラブル対策

犬の噛みつきトラブルを防ぐためには、適切な対策が必要不可欠です。
飼い主は、犬の行動を理解し、原因を特定することから始め、適切な飼育環境とトレーニングを提供することが重要です。
状況に応じた対策や獣医師への定期的な検診も欠かせません。
犬の行動を理解し、原因を特定する
犬の噛みつきトラブルを防ぐ第一歩は、犬の行動を理解し、原因を特定することです。
飼い主は、日頃から犬の行動をよく観察し、噛みつきが起こった状況を詳細に分析する必要があります。
ストレスや恐怖心、痛みなどが原因となっている場合があるため、それらの要因を特定することが重要です。
飼い主だけでは原因の特定が難しい場合は、獣医師などの専門家に相談しましょう。
適切な飼育環境とトレーニング
犬の噛みつきトラブルを防ぐには、適切な飼育環境とトレーニングが欠かせません。
十分な運動と遊びの機会を提供する
犬がストレスを溜め込まないように、十分な運動と遊びの機会を提供することが重要です。
散歩やドッグランでの運動、オモチャを使った遊びなどを通して、犬の心身のバランスを保ちましょう。