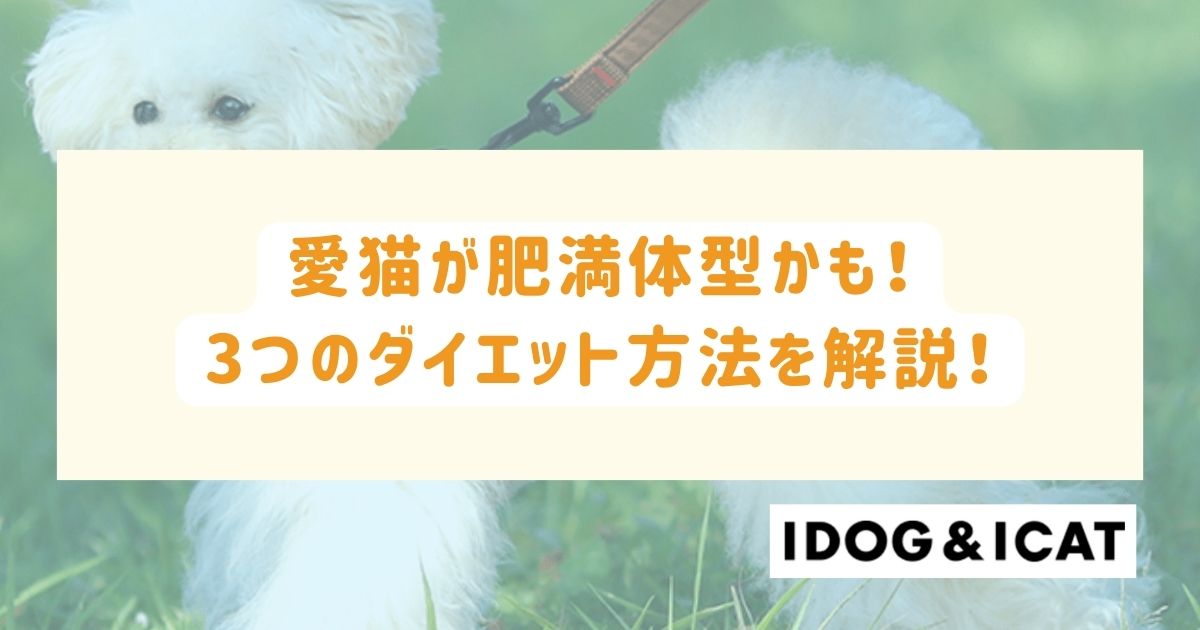
目次
あなたの愛猫が健やかに過ごせるかどうかは、飼い主の健康管理によります。
それには十分な運動や睡眠などが思い浮かびますが、忘れてはならないのは適切な食事管理です。
しかし、猫の肥満について、正しい知識を持っている飼い主さんは意外と少ないかもしれません。
愛猫の肥満に関して、具体的に以下のような疑問を感じたことはありませんか?
- 猫が太り過ぎて動かなくなったらどうしたらいい?
- 猫のダイエットのやり方は?
- 猫の肥満になるのは何キロ?
実は、猫の肥満は深刻な健康問題を引き起こす可能性があり、適切なダイエット法が必要不可欠です。
肥満は、関節炎や糖尿病などの健康リスクを高め、愛猫の生活の質を大きく低下させます。
そこで本記事では、愛猫の肥満度のチェック方法から、食事管理、運動促進、生活習慣の改善までを網羅的に解説します。
愛猫のために少しでも興味のある方は、ぜひ最後までご覧くださいね!
猫が肥満になる原因
食べ過ぎ・運動不足
猫が肥満になる主な原因は、食べ過ぎと運動不足です。
猫は元来、狩猟動物であり、野生環境では獲物を捕まえるために多くのエネルギーを消費します。
しかし、室内飼いの猫は、狩猟の必要がなく、食事も飼い主によって管理されているため、必要以上のカロリーを摂取してしまう傾向にあります。
飼い主のケア不足も、猫の肥満につながります。
例えば、猫の食事量を適切に管理せず、自由に食べさせてしまうことで、猫は必要以上のカロリーを摂取してしまいます。
また、猫の運動不足も問題です。
室内飼いの猫は、基本的に運動の機会が限られているため、飼い主が積極的に遊びや運動を提供しないと、活動量が低下し、肥満につながります。
ストレスによる過食も、猫の肥満の原因の一つです。
環境の変化や飼い主との関係性の問題などがストレスとなり、猫がストレス解消のために過食してしまうことがあります。
ストレスを感じている猫は、食事に執着しがちで、常に食べ物を求めるようになります。
去勢・避妊手術を受けた猫も、肥満になりやすい傾向があります。
これらの手術は、猫の性ホルモンのバランスを変化させ、代謝の低下を引き起こします。
その結果、去勢・避妊後の猫は、同じ量の食事を摂取しても体重が増加しやすくなります。
また、手術後の猫は、活動量が低下する傾向もあり、運動不足にもつながります。
これらのことから飼い主は、肥満の要因を理解し、適切な食事管理と運動の提供に努めることが重要です。
病気や体質
猫の肥満は、病気や体質が関係している場合もあります。
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足する病気です。
このホルモンは、代謝を促進する働きがあるため、分泌が不足すると代謝が低下し、体重が増加しやすくなります。
猫の甲状腺機能低下症は、中高齢の猫に多く見られ、肥満の原因となります。
糖尿病も、猫の肥満と関連がある病気です。
肥満の猫は、インスリン抵抗性を引き起こしやすく、血糖値のコントロールが難しくなります。
その結果、糖尿病を発症するリスクが高まります。
糖尿病を発症した猫は、エネルギーを効率的に利用できなくなるため、体重が増加しやすい傾向があります。
クッシング症候群は、副腎皮質ホルモンの分泌過剰により発症する病気です。
このホルモンは、代謝や免疫機能に関与しており、分泌が過剰になると、体脂肪の蓄積や筋肉の分解が進み、肥満になりやすくなります。
これらの病気は、猫の代謝に直接的な影響を与え、肥満を引き起こします。
飼い主は、猫の体重増加や体型の変化に注意し、病気の可能性を疑った場合は、速やかに獣医師に相談することが大切です。
早期発見と適切な治療により、病気による肥満を改善し、猫の健康を維持することができます。
年齢
猫の肥満は、加齢に伴って発生しやすくなります。
年齢とともに、猫の代謝機能が低下し、エネルギー消費量が減少するためです。
子猫や若い猫は、成長に必要なエネルギーを消費するため、比較的肥満になりにくい傾向があります。
しかし、成猫になると、エネルギー消費量が減少し、同じ量の食事を摂取していても体重が増加しやすくなります。
特に、中高齢の猫は、代謝機能の低下が顕著になるため、肥満のリスクが高くなります。
加齢に伴う運動量の減少も、肥満の原因の一つです。
高齢の猫は、関節の問題や筋力の低下により、活動量が減少します。
また、高齢猫は、睡眠時間が長くなる傾向もあり、エネルギー消費量がさらに低下します。
飼い主は、猫の加齢に伴う変化を理解し、適切な食事管理と運動の提供に努めることが重要です。
品種
猫の肥満は、品種によっても発生しやすさが異なります。
特定の猫種は、他の猫種と比較して肥満になりやすい傾向があるのです。
ペルシャ猫は、その長い被毛と穏やかな性格から、室内飼いに適した猫種として人気があります。
しかし、ペルシャ猫は運動量が少なく、エネルギー消費量が低いため、肥満になりやすい傾向があります。
また、ペルシャ猫は、呼吸器系の問題を抱えていることが多く、肥満はその症状を悪化させる可能性があります。
参考:ペルシャは猫の王様!その性格や特徴は?チンチラとの違いも解説! #138
メインクーンは、大型の猫種で、体重が7kg以上になることもあります。
メインクーンは、もともと大きな体格の猫種ですが、肥満になると関節への負担が大きくなり、運動器疾患のリスクが高まります。
また、メインクーンは、食欲旺盛な傾向があるため、飼い主が食事量を適切に管理しないと、肥満になりやすくなります。
参考:鳴き声が独特なメインクーンってどんな猫?飼い方のコツと注意点を徹底解説! #127
ラグドールは、柔らかな被毛と抱っこを好む性格から、多くの飼い主に愛されている猫種です。
しかし、ラグドールは、他の猫種と比較して代謝が遅く、エネルギー消費量が低いため、肥満になりやすい傾向があります。
また、ラグドールは、関節の問題を抱えていることが多く、肥満はその症状を悪化させる可能性があります。
参考:ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
これらの猫種を飼育する際は、適切な食事管理とダイエットが必要です。
飼い主は、猫種の特性を理解し、適切なカロリー管理を行うことが重要です。
猫の肥満が引き起こす深刻な問題
猫の肥満は、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。
肥満は単なる見た目の問題ではなく、猫の健康に深刻な影響を与えます。
飼い主は、肥満の猫が抱えるリスクを理解し、適切な予防と管理に努めることが大切です。
糖尿病
肥満は、猫の糖尿病発症リスクを高めます。
猫の糖尿病は、インスリンの作用不足や分泌不足により、血糖値が上昇する病気です。
肥満の猫は、インスリン抵抗性を引き起こしやすく、血糖値のコントロールが難しくなります。
糖尿病を発症すると、猫は以下のような深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
- 血管や神経へのダメージ:高血糖状態が続くと、血管や神経が傷つき、全身の臓器に悪影響を及ぼします。
- 白内障:高血糖により、眼のレンズが混濁し、視力障害や失明につながることがあります。
- 腎不全:糖尿病による血管障害は、腎臓の機能低下を引き起こし、腎不全のリスクを高めます。
運動器疾患
肥満は、猫の関節や骨に大きな負担をかけ、運動器疾患のリスクを高めます。
関節炎は、肥満の猫に多く見られる運動器疾患の一つです。
過剰な体重は、関節に負担をかけ、関節軟骨の損傷や炎症を引き起こします。
関節炎を発症した猫は、痛みや可動域の制限により、活動量が低下し、さらに肥満が悪化する悪循環に陥ります。
股関節脱臼も、肥満の猫に多く見られる運動器疾患です。
過剰な体重は、股関節に負担をかけ、関節の脱臼や亜脱臼を引き起こします。
股関節脱臼は、激しい痛みを伴います。
脂質異常症
肥満は、猫の脂質代謝に悪影響を及ぼし、脂質異常症を引き起こす可能性があります。
脂質異常症は、血中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が異常に高くなる病気です。
脂質異常症を引き起こす要因の一つは、脂質沈着です。
肥満の猫は、体内に過剰な脂肪が蓄積され、肝臓や血管に脂質が沈着しやすくなります。
肝臓への脂質沈着は、肝臓の機能低下や炎症を引き起こし、肝炎のリスクを高めます。
膵炎も、脂質異常症と関連があります。
肥満の猫は、膵臓に脂肪が蓄積されやすく、膵炎を引き起こす可能性があります。
膵炎は、激しい腹痛や嘔吐を伴う重篤な病気で、適切な治療が必要です。
呼吸器疾患
肥満は、猫の呼吸機能に負担をかけ、呼吸器疾患のリスクを高めます。
肥満の猫は、呼吸困難を引き起こす可能性があります。
過剰な体重は、胸腔や腹腔を圧迫し、肺の拡張を妨げます。
その結果、猫は呼吸困難を感じ、運動時の息切れなどが見られることが多くなるのです。
愛猫の肥満度をチェックする方法
愛猫が健康で幸せな生活を送るためには、適切な体重管理が欠かせません。
肥満は、猫の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、飼い主が定期的に愛猫の肥満度をチェックし、早期発見と適切なダイエットを行うことが重要です。
以下では、愛猫の肥満度をチェックする3つの方法を詳しく説明します。
体重測定
愛猫の体重を定期的に測定し、記録することは、肥満度をチェックする上で重要な方法の一つです。
理想体重からの乖離を把握することで、肥満の早期発見や予防に役立ちます。
猫の理想体重は、猫種や年齢によって異なります。
例えば、成猫の平均的な体重は、以下のような範囲が目安とされています。
- 小型猫(シャム猫など):2.5~4.0kg
- 中型猫(アメリカンショートヘアなど):4.0~6.0kg
- 大型猫(メインクーンなど):5.0~8.0kg
ただし、これらはあくまでも目安であり、個々の猫の体格や骨格によって、理想体重は異なります。
愛猫の理想体重が不明な場合は、獣医師に相談して確認することをおすすめします。
体型チェック
引用元:環境省-飼い主のためのペットフード・ガイドライン–
愛猫の体型を観察することは、肥満度をチェックする上で欠かせない方法です。
肥満の猫は、体型に特徴的な変化が現れるため、飼い主が日頃から愛猫の体型に注目することが大切です。
以下の点に注目して、愛猫の体型をチェックしてみましょう。
- 背中から腰にかけてのくびれが確認できるか
健康的な体重の猫は、背中から腰にかけてくびれが確認できます。くびれがない、または不明瞭な場合は、肥満の可能性があります。
- お腹が垂れ下がっていないか
健康的な体重の猫は、お腹が引き締まっています。お腹が垂れ下がっている、または下腹部に脂肪が蓄積している場合は、肥満の可能性があります。
- 肋骨が触れるか
健康的な体重の猫は、肋骨が薄い脂肪層で覆われており、触れることができます。肋骨が触れにくい、または触れない場合は、肥満の可能性があります。
これらの体型の特徴は、猫種によって多少異なる場合がありますが、くびれがなく、お腹が垂れ下がっている場合は、肥満の兆候として注意が必要です。
BMI(ボディマス指数)
BMI(ボディマス指数)は、人間の肥満度を判定する指標として広く使われていますが、猫の肥満度をチェックする上でも参考になります。
BMIは、体重と身長(体長)から算出される指標で、猫の体格を考慮した肥満度の目安となります。
猫のBMIは、以下の式で計算します。
BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)例えば、体重5kg、身長50cmの猫のBMIは、以下のように計算されます。
BMI = 5kg ÷ (0.5m × 0.5m) = 20この場合、BMIは20となり、「肥満」と判定されます。
一般的に、猫のBMIは以下のような範囲が目安とされています。
- 標準体重:2.5~4.0
- 肥満:5.0以上
ただし、BMIは猫種や体型によって異なるため、これもあくまで目安として考える必要があります。
以上の3つの方法を組み合わせることで、愛猫の肥満度を総合的にチェックすることができます。
飼い主は、定期的に愛猫の体重測定、体型チェック、BMIの計算を行い、肥満の兆候を早期に発見するよう心がけましょう。
愛猫の肥満に効果的なダイエット方法
肥満は、猫の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、適切なダイエット方法を選択することが重要です。
飼い主は、愛猫の健康を守るために、適切な食事管理、運動の促進、生活習慣の改善に取り組む必要があります。
食事管理
食事の管理は、猫の肥満治療に欠かせない方法であり、カロリーコントロールと栄養バランスの調整が鍵となります。
カロリー計算によるフード量調整
猫の肥満治療では、カロリー制限が重要な役割を果たします。
猫の理想体重を達成するために必要なカロリー量を計算し、フード量を調整する必要があります。
まず、猫の現在の体重と目標体重を設定します。
そして、目標体重を維持するために必要なカロリー量を計算します。
一般的に、成猫の1日あたりのカロリー必要量は、以下の式で計算されます。
1日のカロリー必要量 = 体重(kg)× 30 + 70
例えば、目標体重が4kgの場合、1日のカロリー必要量は、「4 × 30 + 70 = 190kcal」となります。
次に、猫のフードのカロリー含有量を確認し、1日に与える量を決定します。
カロリーコントロールフードを活用することで、効果的なダイエットが可能です。
カロリーコントロールフードは、通常のフードよりもカロリーが低く設定されているため、適量を与えることで、自然とカロリー制限ができます。
ちなみに食事療法を始める際は、徐々にフード量を減らしていくことが大切です。
急激な食事量の減少は、猫にストレスを与える可能性があります。
また、必要な栄養素が不足しないよう、獣医師と相談しながら進めることも重要です。
食事回数を増やす
猫の食事回数を増やすことも、肥満治療に効果的です。
1日の食事回数を2回から3~4回に増やし、1回あたりの食事量を減らすことで、猫の満腹感を維持しながら、カロリー制限を行うことができます。
猫は、もともと狩猟動物であり、1日に何度も小さな獲物を捕らえて食べる習性があります。
この習性を活かし、少量ずつこまめに与えることで、猫の満足度を高め、ストレスを軽減することができます。
ウェットフードを取り入れる
ウェットフードは、水分量が多く、低カロリーであるため、猫の満腹感を得やすく、ダイエットに適しています。
猫は、本来、水分摂取の大部分を餌から得る動物です。
ウェットフードは、水分含有量が80%程度と高く、猫の自然な食生活に近い形態です。
また、ウェットフードは、ドライフードと比較してカロリー密度が低いため、たくさん食べてもカロリー過多になりにくいという特徴があります。
ウェットフードを取り入れる際は、以下の点に注意しましょう。
- ウェットフードのみでは、必要な栄養素が不足する可能性があるため、ドライフードとの組み合わせが望ましい。
- ウェットフードは、開封後の傷みが早いため、適量を与え、残りは冷蔵庫で保管する。
- ウェットフードは、歯垢がつきやすいため、定期的な歯磨きやデンタルケアが必要。
手作りフード
手作りフードは、猫の体質や体調に合わせた栄養バランスを調整できる利点があります。
市販のフードでは、猫の個別のニーズに対応しきれない場合、手作りフードを取り入れることで、より精度の高いダイエット管理が可能です。
手作りフードを準備する際は、以下の点に注意しましょう。
- 新鮮で安全な食材を使用する。
- 猫に必要な栄養素(タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルなど)をバランスよく含むレシピを選ぶ。
- 調理方法は、シンプルで消化しやすいものを選ぶ(茹でる、蒸すなど)。
- 手作りフードは、保存がきかないため、作り置きせず、必要な量だけ準備する。
ただし、手作りフードは栄養バランスを考えるのは容易ではないため、獣医師や動物栄養学の専門家に相談し、適切なレシピを決定することが大切です。
おやつを見直す
おやつは、猫にとって大きな楽しみの一つですが、肥満の原因にもなります。
高カロリーのおやつを避け、低カロリーのおやつを選択することが重要です。
肥満の猫に適したおやつは、以下のような特徴があります。
- カロリーが低い(1個あたり10kcal以下)。
- 脂肪分が少ない。
- 食物繊維が豊富。
- 噛みごたえがあり、満足感が得られる。
また、おやつの選択以外にも、与え方の工夫が必要です。
おやつの与える量を制限することで、余分なカロリー摂取を防ぐことができます。
ちなみに、1日のおやつのカロリーは、1日の総カロリーの10%以内に抑えることが理想的です。
運動の促進
運動の促進も、猫の肥満対策に欠かせない方法の一つです。
運動は、エネルギー消費を促進し、脂肪燃焼を助けます。
また、運動不足は、肥満だけでなく、関節炎や糖尿病などの健康問題のリスクを高めるため、適度な運動は猫の健康維持に欠かせません。
遊びを取り入れる
猫は、遊びを通して運動することが多いため、遊びを取り入れることが効果的です。
猫じゃらしやレーザーポインターを使って、愛猫と一緒に遊びましょう。
また、猫用のトンネルやキャットタワーを設置することも有効です。
トンネルを通り抜けたり、キャットタワーを登ったりすることで、猫は全身を使って運動することができます。
遊びの際は、猫の運動量に合わせて、休憩を取り入れることが大切です。
猫は、短時間の激しい運動を好む傾向があるため、「5~10分程度の遊びを、1日数回行う」のが理想的です。
室内環境を整える
室内飼いの猫は、運動量が少なくなりがちです。
そのため、猫が自発的に運動するための環境を整えることが重要です。
まず、猫が運動できるスペースを確保しましょう。
家具の配置を工夫し、猫が走り回れる空間を作ります。
また、キャットタワーなどを設置し、上下運動を促すのも効果的です。
次に、猫用のおもちゃを用意しましょう。
ボール、ぬいぐるみ、羽のおもちゃなど、猫の興味を引くおもちゃを複数用意し、ローテーションで与えることで、飽きを防ぎ、運動意欲を高めることができます。
一緒に遊ぶ時間を増やす
飼い主が積極的に猫と遊ぶことで、猫の運動量を増やし、猫とのコミュニケーションを深めることができます。
飼い主が主導して遊ぶことで、猫は飼い主との絆を感じ、遊びへの意欲が高まります。
また、飼い主が遊びに参加することで、猫の運動時間や強度をコントロールすることができます。
猫と一緒に遊ぶ時間を、1日30分程度確保するのが理想的です。
ただし、猫の体力や気分に合わせて、無理のない範囲で行うことが大切です。
生活習慣の改善
猫の肥満には、食事管理や運動の促進だけでなく、生活習慣の改善も重要です。
不適切な生活習慣は、猫のストレスを増大させ、過食や運動不足を招く可能性があります。
ストレスを減らす
猫のストレスを減らすことは、肥満治療に欠かせません。
ストレスは、猫の食欲や行動に大きな影響を与えます。
ストレスを感じている猫は、過食や不活発になる傾向があるためです。
ストレス軽減のためには、まず、猫の生活環境を整えることが大切です。
清潔で快適な環境を維持し、猫の隠れ家やくつろぎスペースを確保しましょう。
また、猫の好みに合わせて、ベッドやキャットタワーを用意することで、安心感を与えることができます。
次に、飼い主が猫の遊び相手になることも重要です。
定期的に猫と遊ぶことで、ストレス発散と運動不足の解消につながります。
さらに、ブラッシングやマッサージは、猫のリラックス効果が期待できます。
十分な睡眠時間を確保する
猫の十分な睡眠時間を確保することは、健康維持に欠かせません。
猫は、1日の大部分を睡眠に費やす動物です。
適切な睡眠は、ストレス軽減や免疫力の向上に役立ちます。
そのためにも猫が安心して眠れる環境を整えましょう。
暗静な場所に、心地よいベッドや段ボールを用意し、猫の休息スペースを確保します。
また、昼夜のリズムを整えるために、日中は自然光を取り入れ、夜は照明を落とすなどの工夫が有効です。
定期的な健康診断を受ける
定期的な健康診断は、肥満の進行状況を把握し、病気の早期発見・早期治療につなげるために重要です。
肥満の猫は、定期的な体重測定と体型チェックが欠かせません。
体重の変化を記録し、肥満の改善具合を評価します。また、体型の変化を観察し、脂肪の付き方や筋肉量の変化を把握します。
健康診断では、内臓脂肪の蓄積具合や内臓機能の状態を確認することができます。
肥満は、心臓病や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めるため、早期発見と適切な治療が重要です。
獣医師に相談する
肥満の適切なダイエット方法について、獣医師に相談することも効果的です。
獣医師は、猫の健康状態や生活環境を考慮し、個々の猫に合ったダイエット方法を提案してくれます。
食事管理面では、愛猫の栄養需要を計算し、適切なフードの種類や量を決定してくれます。
また、必要に応じて、サプリメントや薬の使用を検討することもあります。
運動面では、猫の運動能力や関節の状態を評価し、適切な運動方法や時間を決定します。
高齢猫や関節炎を持つ猫には、低強度の運動プログラムを推奨することもあります。
生活習慣の改善では、猫のストレス要因や睡眠環境についてアドバイスを受けることができます。
獣医師は、飼い主の生活スタイルを考慮し、実行可能な改善策を提案してくれます。
このように愛猫のダイエット方法には、食事管理、運動の促進、生活習慣の改善を組み合わせることが効果的です。
それぞれの方法は、互いに関連し合っており、バランスの取れたアプローチが求められます。
愛猫のために、今日から肥満予防とダイエットに早速取り組んでみましょう。
愛猫が太り過ぎて動かなくなったら?
愛猫が太り過ぎて動かなくなったら、以下のことを実践しましょう。
- 獣医師に相談する
- 無理に動かさない
- 少しずつ運動を取り入れる
- 遊びを取り入れる
- 環境を整える
獣医師に相談する
愛猫が太りすぎて動かなくなった場合、まずは獣医師に相談することが大切です。
極端な肥満は、糖尿病や関節炎など、様々な健康問題のリスクを高めます。
獣医師は、愛猫の肥満の原因が病気によるものかどうかを検査し、安全かつ効果的なダイエット方法を指導してくれます。
無理に動かさない
太りすぎた猫を無理に動かすと、関節に負担がかかり、怪我や病状悪化のリスクがあります。
無理な運動は避け、猫の体調に合わせて適切な運動量を心がけましょう。
少しずつ運動を取り入れる
無理なく運動を取り入れるために、短時間から始め、徐々に時間を延ばしていくことが重要です。
また、猫が興味を引くおもちゃを使って遊び、飼い主と一緒に遊ぶ時間を増やすことも効果的です。
猫の運動量を無理なく増やすことが、肥満解消の鍵となります。
遊びを取り入れる
猫が興味を引く様々な種類のおもちゃを用意し、一緒に遊ぶことで、運動量を増やすことができます。
猫じゃらしやレーザーポインターなどを使った遊びは、猫の運動不足解消に効果的です。
環境を整える
猫が自由に動き回れるように、室内環境を整えましょう。
段差を設けたり、キャットタワーを設置したりすることで、猫の運動機会を増やすことができます。
また、猫が快適に過ごせる空間を作ることで、ストレスを軽減し、肥満解消に役立ちます。
愛猫の肥満問題を適切なダイエット法で解消しよう!
愛猫の肥満は、飼い主にとって見過ごせない深刻な問題です。
肥満は、関節炎や糖尿病などの健康リスクを高め、猫の生活の質を大きく低下させます。
しかし、適切なダイエット法を実践することで、愛猫の肥満を解消することができます。
まず、愛猫の肥満度をチェックすることが大切です。
ダイエットは、食事管理、運動の促進、生活習慣の改善を組み合わせて行います。
また、ダイエットの過程では、獣医師との連携が欠かせません。
定期的な健康診断で肥満の進行状況を把握し、個々の猫に合ったダイエット方法を相談しましょう。
急激な食事制限は避け、猫の健康状態に合わせて徐々に進めることが大切です。
ダイエットは一朝一夕では成果が出ませんが、諦めずに根気よく取り組むことが重要です。
愛猫の健康のために、辛抱強くがんばってあげてください!
Q&A
大切な家族である愛猫に良質なアイテムを!【IDOG&ICAT】
日々を一緒に過ごし、いつもあなたを癒してくれる愛猫は、れっきとした家族の一員です。
そんな愛猫の一生は、飼い主であるあなたと過ごす時間で決まります。
どうせなら楽しく、リラックスできる時間を長く作ってあげたいですよね。
また、あなた自身も愛猫の可愛い姿や、楽しんでいる姿をできるだけ多く見たくありませんか?
幸せな時間を創出する1つの手段が、飼い猫のために作られたグッズやアイテムです。
実はこれらのアイテムは、愛猫がリラックスできる時間を生み出すだけではなく、健康状態の改善にも大きく役立ちます。
ペットの幸福度を高めながら体のケアもできるなんて、一石二鳥ですよね!
もし、あなたの愛猫や飼い主さんが以下のように感じているのであれば、猫用のアイテムで解決できる可能性があります。
- 愛猫がストレスを感じてるかも…
- 毛玉が多くて悩んでいる
- 食事を食べるときの体勢がしんどそう
このような場合、ストレス発散と爪の健康にも役立つ「爪とぎ」や毛玉対策の「グルーミングブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが効果的です。
とはいえ、アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。
しかし、あなたの愛猫にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。
猫グッズを扱っている通販サイトは数多く存在しますが、せっかくならIDOG&ICATがオススメです。
IDOG&ICATは創業33年の縫製工場を母体とするペットグッズメーカーです。
縫製工場から派生した老舗メーカーだからこそ、品質にこだわった最高級の猫グッズをお客様に提供しています。
IDOG&ICATの大きな特徴は、ペットのことを第一優先に考えた商品づくりです。
愛猫が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。
あなたと愛猫がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?
人気記事ランキング
人気記事ランキング
希少種ミヌエットはどんな猫?性格や特徴、育て方のポイントも解説!
93294views
猫がふみふみする理由とふみふみしない猫との違いとは? #50
65052views
ベンガルキャットが持つ意外な性格とは?しつけは子猫のときから行おう! #115
55132views
アメリカンショートヘアはどんな性格?オスとメスの違いも徹底解説! #77
49540views
猫が急に走り出す7つの理由とは?走る猫の注意点とその対処法も解説! #82
48014views
飼い猫が脱走したらどうしたらいい?探し方と事前にできる対策とは? #48
43381views
ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
36666views
猫のロシアンブルーってどんな性格?「猫ではない」と言われるほどの忠誠心を持つ #129
36561views
