子犬の噛み癖がひどいときはどうしたらいい?改善する3つのポイント
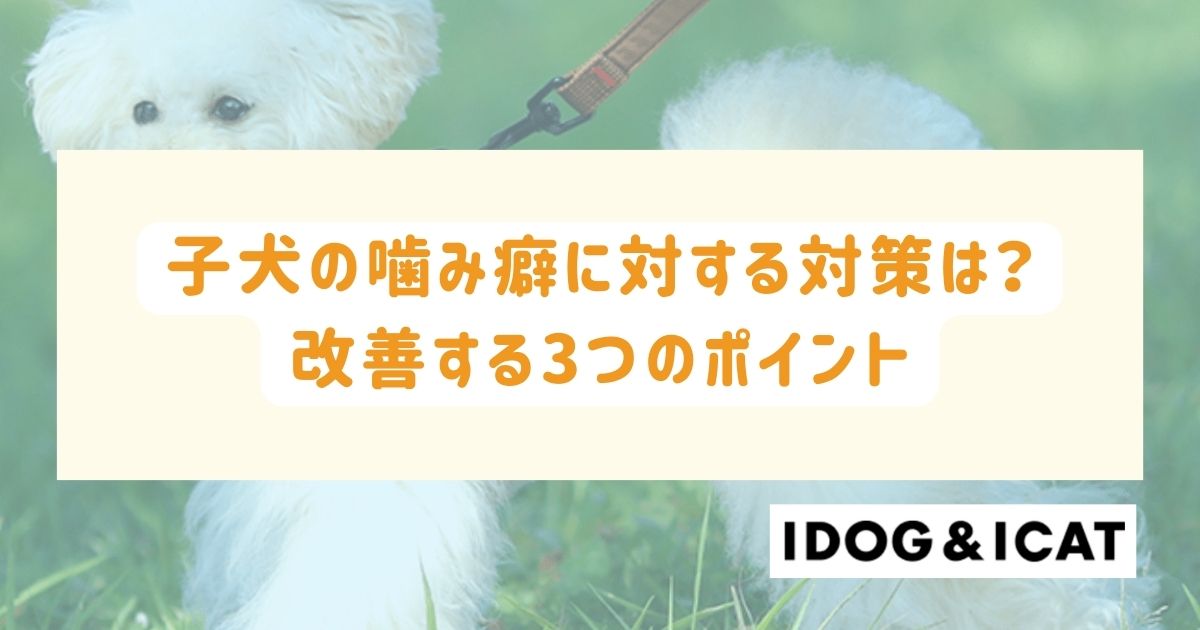
目次
あなたの可愛い子犬が家族の一員として幸せに暮らすためには、飼い主の育て方にかかっています。
しかし、生き物である以上、なかなか思うようにいかないこともありますよね。
特に子犬の噛み癖は、育てるプロセスで起こり得る課題の一つです。
実際、以下のような悩みや疑問を感じていませんか?
- 子犬が噛むのをやめさせる方法は?
- 子犬が噛んだとき、どう叱ればいい?
- 子犬の噛み癖はいつ頃ピーク?
実は、子犬の噛み癖への対処法は、適切なやり方を行えばきちんと改善することが可能です。
しかし、間違った改善方法を行なっている人もいます。
そこで本記事では、子犬の噛み癖を改善する3つのポイントだけでなく、その予防策まで網羅的に解説します。
簡潔に記載しているので、少しでも気になる方はぜひ最後までご覧くださいね!
子犬の噛み癖の理由
子犬の噛み癖は、「単なる癖」だけでなく、その背景にはいくつか理由が存在します。
具体的には、以下の通りです。
- 成長過程の一環
- コミュニケーション
- ストレスや不安
- 歯の生え変わりによる痛み
- 遊びの延長
それぞれ確認していきましょう。
参考:ASPCA-Mouthing, Nipping and Biting in Puppies–
成長過程の一環
子犬の噛み癖は成長の一環としても起こります。
生後数ヶ月は、身の回りのものに対する理解を深めるための重要な時期です。
つまり、この時期に噛むことは新しいものに慣れ、それらを認識する1つの手段になります。
コミュニケーション
噛み癖は、子犬が他の犬や人とコミュニケーションを取る方法でもあります。
遊びの中で噛むことによって、相手の反応を観察しつつ、社会的な関係性を築くのです。
このプロセスを通じて、噛む力の調節やいつ噛むべきでないかなどを理解することができます。
ストレスや不安
ストレスや不安も、子犬の噛み癖の一因です。
新しい環境や状況に対する不安から、安心感を求めて「噛む」という行為を取ります。
安定した環境と安心できる存在が周囲にあることで、このような噛み癖は徐々に減少します。
歯の生え変わりによる痛み
生後3~6ヶ月の間に、子犬は乳歯から永久歯へと生え変わります。
この過程で生じる歯茎の痛みや違和感を和らげるために、噛む行動が増えることがあります。
この期間の対策として、噛みつき防止のおもちゃなどを与えることが効果的です。
遊びの延長
最後に、遊びの一環としての噛む行動も見られます。
子犬は遊びを通じてエネルギーを発散させます。
つまり、このケースでは「噛む=遊び」として捉えています。
適切な遊び方を教えることで、不適切な噛み癖を抑えることが可能です。
子犬の噛み癖を改善する3つのポイント
子犬の噛み癖を効果的に改善するためには、誤った対応を避け、適切な行動を促進し、根気強く継続することが重要です。
これらのポイントを実践することで、子犬の不要な噛み癖は軽減できます。
噛み癖を悪化させないNG行動
まずは、誤った「NG行動」を確認していきましょう。
噛んだときに手を引っ込める
手を引っ込める行為は、子犬にとって遊びの一環と認識され、噛み癖をさらに刺激することになります。
このような反応を取ることで、「噛む=遊び相手してくれる」など誤解を生んでしまいます。
大きな声で叱る
大きな声で叱ることは、子犬を怖がらせ、ストレスにつながります。
これは逆効果であり、信頼関係の構築を妨げてしまいます。
体罰を与える
体罰は絶対に避けましょう。
これは子犬との信頼関係を壊し、恐怖心やさらなる攻撃性を引き起こす原因となります。
子犬の噛み癖を抑制する方法
大前提として重要なことは、噛んだ理由を考えることです。
単なる噛み癖ではない場合、子犬は何らかの意図があってその行動を取っています。
そのため、一概に「これはダメな噛み癖だ」と決めつけず、噛んだ理由を考えてみましょう。
もしかしたら、何かを訴えているのかもしれません。
また、特定の行動に対して、噛み癖がある場合はその理由も想像してみましょう。
「ご飯を取られたくない」と思って噛むのであれば、人が食べ物を奪わないことを認識させる必要があります。
靴下などの衣類を噛む場合、過去にその引っ張り合いになり、「遊んでもらっている」と誤認している可能性もあります。
このような中で、簡単にできる方法を解説します。
噛みつき防止のおもちゃを与える
噛んでも良いものを与えることで、余計なものを噛まれず、子犬の噛み癖を発散させることができます。
噛んだら「ダメ」と伝える
しつけの一環として、噛んだら「ダメ」と教えましょう。
例えば、子犬が人の手や足を噛んだとき、すぐに「ダメ」とはっきりと言いながら、その場を離れます。
これにより、子犬に噛む行為が飼い主の注意を引いたり、遊びの合図ではないことを理解させることができます。
噛むことの代わりにできる行動を教える
噛む代わりの行動を促すことで、子犬の注意を噛むこと以外に向けることができます。
例えば、子犬が噛もうとしたときに、噛みつき防止用のおもちゃを口に持たせたり、「お座り」や「待て」といった指示に従うようにトレーニングすることなどが効果的です。
参考:犬が吠えることをやめさせるにはどうしたらいい?5つのしつけ方法を解説!#201
子犬の噛み癖が治るまでの期間
子犬の噛み癖は、一朝一夕で改善されるものではありません。
一般的に、数週間から数ヶ月かかると言われています。
個体差があるため、早くに治る子もいれば、なかなか治らない子もいます。
そのため、噛み癖の改善には、それ相応の時間と根気強さが必要です。
適切な対応を行いつつも、焦らず長期的に取り組みましょう。
噛み癖がひどい場合は専門家へ
噛み癖がどうしても改善されない、または特にひどい場合、専門家に助けを求めることも1つの手段です。
噛む行為の背景には、痛みや不快感も考えられます。
この場合、獣医師による健康診断を通じて、その原因を特定させることが可能です。
また、ドッグトレーナーは、犬の行動を修正するための知識や経験が豊富です。
このことから、犬の行動を理解し、状況に応じた適切なトレーニング方法を提案してくれます。
専門家以外に、しつけ教室に参加することも有効な手段です。
こちらも愛犬のために、適切なしつけ方法や、改善策を教えてもらえます。
愛犬の噛み癖を予防する7つの対策
愛犬が現在噛み癖がなくても、今後それが生じる可能性はあります。
それに対して、あらかじめ以下の7つの予防策を実践することで、噛み癖のリスクを減らすことが可能です。
- 噛む対象を制限する
- 安全なサークルを用意する
- 適切な運動量を知る
- さまざまな種類の遊びをさせる
- ストレスの原因を特定する
- ストレスを解消させる
- 安心できる環境を作る
噛む対象を制限する
噛む対象を制限するとは、愛犬が噛んではいけないものに触れないようにすることです。
これにより、飼い主が見ていない間でも、余計なものを噛む心配はなくなります。
安全なサークルを用意する
家の中に安全なサークルを用意することも、効果的な1つの予防策です。
特に留守番の際には、安全なサークルや遊ぶスペースを用意することで、気兼ねなく遊んだり、ストレスを発散させられます。
参考:犬が留守番できる時間は?留守番させるときの5つのポイントも解説!
適切な運動量を知る
犬の健康維持には、適切な運動が不可欠です。
運動によってエネルギーを適切に消費させることで、ストレスや過剰な興奮による噛み癖を予防することができます。
参考:飼い犬を遊ばせる5つの方法とは?おもちゃを使って適度な運動をさせよう!#204
さまざまな種類の遊びをさせる
運動させるといっても、犬の遊びは以下のように種類があります。
- おもちゃでの遊び
- 散歩やランニング
- 知育遊び
一定の遊びだけでなく、さまざまな遊びを通じて、愛犬の好奇心を刺激してあげましょう。
その結果、噛むこと以外にも興味を示す可能性があります。
ストレスの原因を特定する
噛み癖はストレスからくることもあります。
そのため、愛犬の行動や環境を観察し、ストレスの原因を特定してあげましょう。
その原因を取り除くことができれば、愛犬のストレスを軽減し、噛み癖の予防につながります。
参考:飼い犬がストレスを感じているサインとは?4つの発散方法も徹底解説! #182
ストレスを解消させる
長期間にわたるストレスは、噛み癖を含む愛犬の問題行動を引き起こす危険性があります。
そのため、ストレスを定期的に解消してあげることが重要です。
ストレスの解消方法は、適切な運動や飼い主さんとのコミュニケーションなどが挙げられます。
安心できる環境を作る
愛犬が常に安心して過ごせるような環境を整えることが大切です。
安心できない環境であれば、それもまたストレスにつながるからです。
そのため、静かで快適な居場所を作り、愛犬がリラックスできるようにしましょう。
子犬の噛み癖がひどい場合でも根気よく取り組もう!
子犬の噛み癖は、多くの飼い主が直面する問題です。
しかし、飼い主の適切な理解と対策を講じることで、改善することができます。
また、噛み癖は単なる癖ではなく、成長の過程、コミュニケーション手段、ストレスの表現、歯の生え変わりによる痛みや遊びの一環としても起こり得るものです。
そのため、一概に「悪い癖」と決めつけず、まずはその行為に至った理由を考えてみましょう。
案外、何かを訴えているだけかもしれません。
悪い噛み癖を改善するためには、噛み癖を悪化させる行動を避け、代わりに噛みつき防止のおもちゃを使用したり、「ダメ」とわからせるしつけを行うようにします。
とはいえ、噛み癖はすぐに改善を図れるものではありません。
一般的に「数週間から数ヶ月」かかると言われています。
そのため、飼い主は焦らず根気よくその改善に取り組む必要があります。
もし噛み癖がひどい場合や、改善の兆しが見られないときは、専門家に助けを求めることも一つの解決策です。
その際は、獣医師やドッグトレーナーに相談してみましょう。
噛み癖の背後にある健康上の問題や心理的な要因を特定し、適切なトレーニングや対策を提案してくれます。
飼い主としては、可愛い愛犬が将来的にもきちんとマナーのある子に育つように、早めの段階から改善してあげたいですね!
Q&A
Q1: 子犬が噛むのをやめさせる方法は?
A1: 子犬が噛むのをやめさせるには、噛みつき防止のおもちゃを提供し、噛むべきではないものを噛んだ際には「ダメ」と穏やかに伝えることが有効です。また、噛むこと以外に、意識を向けさせることも効果的な手段です。
Q2: 子犬が噛んだとき、どう叱ればいい?
A2: 子犬が噛んだときは、大声で叱るのではなく、「ダメ」と穏やかに伝え、その行動を止めさせることが重要です。噛む行動を止めた後は、正しい行動をしたときに褒めて報酬を与えることで、ポジティブな認識を持たせることができます。
Q3: 子犬の噛み癖はいつ頃ピーク?
A3: 子犬の噛み癖は、特に生後3~6ヶ月の間にピークを迎えます。この時期は歯の生え変わりが発生し、探索欲が高まるため、噛む行動が増加する傾向にあります。
大切な家族である愛犬に良質なアイテムを!【IDOG&ICAT】
日々を一緒に過ごし、いつもあなたを癒してくれる愛犬は、れっきとした家族の一員です。
そんな愛犬の一生は、飼い主であるあなたと過ごす時間で決まります。
どうせなら楽しく、リラックスできる時間を長く作ってあげたいですよね。
また、あなたも愛犬の可愛い姿や、楽しんでいる姿をできるだけ多く見たくありませんか?
幸せな時間を創出する1つの手段が、飼い犬のために作られたグッズやアイテムです。
実はこれらのアイテムは、愛犬がリラックスできる時間を生み出すだけではなく、健康状態の改善にも大きく役立ちます。
ペットの幸福度を高めながら体のケアもできるなんて、一石二鳥ですよね!
もし、あなたの愛犬や飼い主さんが以下のように感じているのであれば、アイテムで解決できる可能性があります。
- 服を着せても嫌がってしまう
- 抜け毛が多くて悩んでいる
- ご飯を食べるときの体勢がしんどそう
このような場合、愛犬にとって着心地の良い「ドッグウェア」や、抜け毛に特化した「ブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが有効的です。
アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。
しかし、あなたの愛犬にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。
犬グッズを扱っている通販サイトは数多く存在しますが、せっかくならIDOG&ICATがオススメです。
IDOG&ICATは創業33年の縫製工場を母体とするペットグッズメーカーです。
縫製工場から派生した老舗メーカーだからこそ、品質にこだわった最高級の犬グッズをお客様に提供しています。
IDOG&ICATの大きな特徴は、ペットのことを第一優先に考えた商品づくりです。
愛犬が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。
あなたと愛犬がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?
人気記事ランキング
人気記事ランキング
希少種ミヌエットはどんな猫?性格や特徴、育て方のポイントも解説!
93294views
猫がふみふみする理由とふみふみしない猫との違いとは? #50
65052views
ベンガルキャットが持つ意外な性格とは?しつけは子猫のときから行おう! #115
55132views
アメリカンショートヘアはどんな性格?オスとメスの違いも徹底解説! #77
49540views
猫が急に走り出す7つの理由とは?走る猫の注意点とその対処法も解説! #82
48014views
飼い猫が脱走したらどうしたらいい?探し方と事前にできる対策とは? #48
43381views
ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
36666views
猫のロシアンブルーってどんな性格?「猫ではない」と言われるほどの忠誠心を持つ #129
36561views
