子犬の鳴き声に対するしつけ方法は?鳴き声でわかる子犬の気持ち
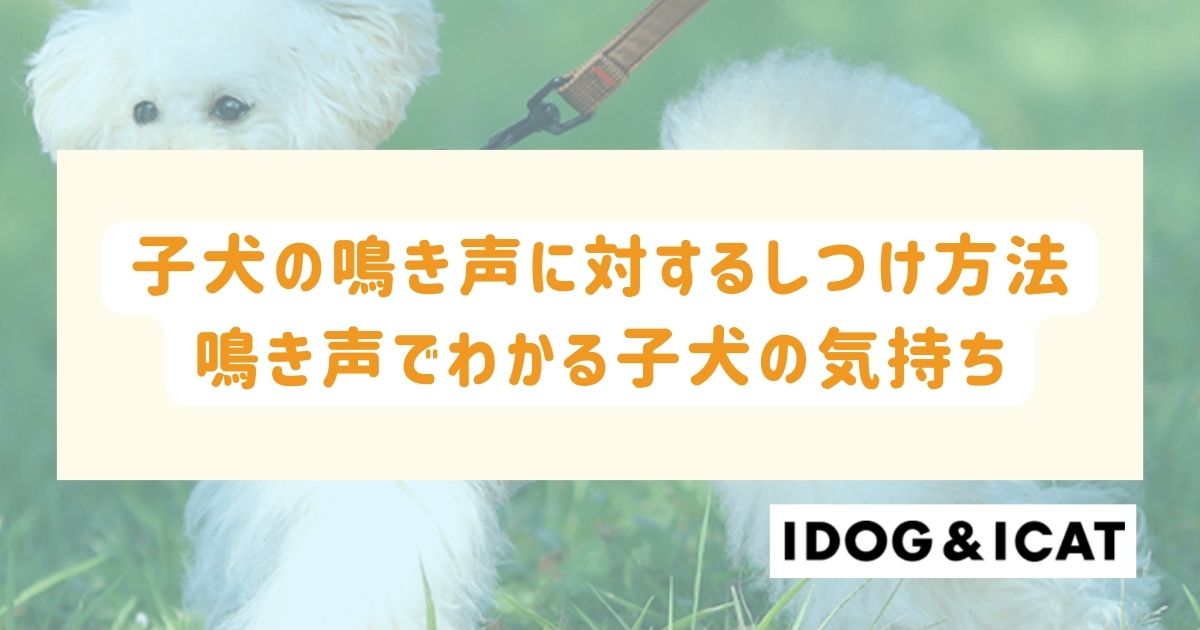
目次
子犬を家族に迎え入れつつも、鳴き声に悩まされている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
子犬は可愛らしい存在ですが、思わぬときに大きな鳴き声を上げて飼い主を驚かせたり、夜中に鳴いて眠れなかったりと、鳴き声は飼い主の頭を悩ませる原因にもなります。
しかし、その鳴き声には必ず何らかの理由や意味があります。
実は、子犬はコミュニケーションの手段として鳴き声を上げているのです。
子犬の鳴き声に関して、具体的に以下のような疑問を感じたことはありませんか?
- 子犬が鳴いているときはどうしたらいい?
- 子犬が4ヶ月で吠えるようになったのですが、どうしたらいい?
- 子犬が遊んでいたら吠えるのはなぜ?
子犬の鳴き声を理解し、適切な対処法を知ることで、鳴き声問題は解決できます。
しかしそれは時には病気のサインかもしれません。
そこで本記事では、子犬の鳴き声の意味や理由、しつけ方法、そして獣医師に相談すべき場合などを詳しく解説します。
簡潔に記載しているので、少しでも気になる方はぜひ最後までご覧ください!
子犬がよく鳴く理由
子犬がよく鳴くことは可愛い反面、飼い主を困らせるケースも少なくありません。
しかし、その鳴き声には必ず理由があります。
そもそも鳴くこと自体、子犬なりのコミュニケーションの手段なのです。
そのため、子犬の鳴き声を理解することは、今後も日々を過ごす飼い主さんにとって必要なことと言えます。
子犬の鳴き声の種類と意味
子犬の鳴き声は一つとは限りません。
喜びや不安、痛みなど、様々な気持ちの表れでもあります。
まずは子犬の鳴き声の種類と意味を押さえましょう。
コミュニケーションのための鳴き声は、遊んでほしい時の「キャンキャン」や甘えたい時の「キュンキュン」など、子犬からの要求です。
一方で、不安や恐怖を表す「ウゥー」のような鳴き声もあります。
ひとり遊びが怖くて鳴く、暗闇を恐れて鳴く、母犬に甘えたくて鳴くといった具合です。
そして時には、体調不良の際の「クゥン」といった痛みや病気のサインになる鳴き声も存在します。
このように様々な気持ちが鳴き声に込められているので、一つひとつの鳴き声の意味を理解することが大切です。
とはいえ、犬は人間同様、個体差が存在するため、鳴き声1つでその意味を断言することはできません。
日々の暮らしの中で子犬を観察しつつ、総合的に判断するようにしましょう。
鳴き声でわかる子犬の気持ちと訴え
子犬によくある鳴き声とその意味を具体的に見ていきましょう。
キャンキャン
小さな体から出る高らかな鳴き声「キャンキャン」は、構ってほしい気持ちや遊びたい要求、トイレに行きたい合図、空腹を訴えている証拠かもしれません。
飼い主さんの愛情や世話を求める子犬の気持ちの現れです。
クゥン
「クゥン」という弱々しく小さな鳴き声は、体調不良のサインかもしれません。
痛みを感じていたり、眠たくて文句を言っていたり、そして寂しさを訴えている可能性もあります。
キュンキュン
「キュンキュン」と甘えた鳴き声は、子犬なりの愛情の現れです。
飼い主さんに甘えたい気持ちや、遊んでほしいという要求を込めて鳴いているのです。
この場合はできるだけかまってあげるようにしましょう。
ウゥー
低くローな「ウゥー」という鳴き声は、警戒心の表れです。
見ず知らずの人や物、状況が怖くて鳴いているのかもしれません。
子犬の気持ちを読み取り、安心させてあげる必要があります。
グルル
「グルル」と低い唸り声を上げていれば、それは威嚇している証拠です。
何かに対して怒っていたり、攻撃的な気持ちを持っている可能性があります。
もしこのように鳴いた場合、その対象が何なのかを判断し、対処することが求められます。
このように鳴き声一つひとつに意味があり、子犬の気持ちが込められています。
更に鳴き声に加えて、その仕草や表情も合わせて見ることで、子犬の気持ちをより正確に推し量ることができるでしょう。
例えば尻尾を振りながら「キャンキャン」と鳴いていれば、さぞ嬉しい気持ちだと理解できます。
また、体を震わせながら「クゥン」と鳴けば、本当に痛みを感じているのかもしれません。
このように鳴き声と仕草を合わせて見ることが大切なのです。
子犬の鳴き声を意識的に観察し、その意味を理解することで、子犬の気持ちに気づきやすくなります。
気持ちに気づけば、適切に対応することもできるようになるはずです。
子犬は言葉を話せなくとも、鳴き声で気持ちを伝えようとしているため、その鳴き声に耳を傾けることが、子犬との絆を深める第一歩になります。
月齢別・鳴き声の変化【成長プロセス】
子犬の鳴き声は、成長過程の中で変化していきます。
生後1〜2ヶ月頃の子犬は、母犬から離れたばかりで不安な気持ちがつのります。
そのため、母犬を恋しがる「キュン」という鳴き声が多く聞かれるものです。
新しい環境に不安を感じ、母犬の気配を求める子犬の気持ちが現れています。
しかし、生後3〜4ヶ月を過ぎる頃から、だんだんと活発になり、「キャンキャン」と遊びたがる鳴き声が増えてきます。
体力や運動能力も付いてくるので、エネルギッシュな面も出てくるのです。
飼い主さんとの絆も深まり、構って欲しい気持ちの表れが多くなるでしょう。
そして生後5〜6ヶ月頃になると、次第に社会性を身につけていきます。
他の犬や人間との関わりを経験することで、コミュニケーションを取ろうとする「キュンキュン」のような鳴き声が増えてくるのが特徴です。
そうして生後7ヶ月を過ぎる頃になると、子犬はほぼ成犬と呼べる存在になります。
鳴き声の種類や出方も徐々に成犬に近くなり、より大人しくなっていきます。
このように子犬の月齢によって、鳴き声の内容や出方が変化していきます。
また、成犬になっても、吠える問題が生じて悩んでいる場合は、以下の記事もご参考ください。
参考:犬が吠えることをやめさせるにはどうしたらいい?5つのしつけ方法を解説!#201
子犬の鳴き声を減らすための具体的なしつけ方法
子犬の鳴き声が多すぎて困っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、適切なしつけを行えば、子犬の鳴き声を減らすことができます。
ここでは、効果的なしつけ方法を5つご紹介します。
トイレトレーニング
鳴き声の大半は、トイレに行きたい合図だったりします。
だからこそ、トイレのしつけをしっかりと行うことが何より大切です。
まずはクレートやサークルなどを使い、トイレの場所を教えましょう。
そして食事や睡眠の後など、トイレに行きたくなりがちなタイミングを把握して見守るのがコツです。
上手くトイレに行けたら、しっかりと褒めてモチベーションアップを図りましょう。
クレートトレーニング
子犬にとって安心できる「わが家」を作り上げることも重要です。
その際、クレートトレーニングが効果的です。
手順を解説します。
クレートに慣れさせる
最初は短い時間から慣らしていきます。
無理強いせずに徐々にクレートでの時間を増やしていきましょう。
クレートを安全な場所にする
クレートの中は快適な環境を整え、子犬が安心できる場所にします。
子犬用のベッドやおもちゃなどを用意するとよいでしょう。
クレートで過ごす時間を徐々に増やす
このようにして慣れていけば、子犬はクレートを自分の”わが家”だと認識するようになり、無駄に鳴く機会が減っていきます。
無視トレーニング
子犬の無駄な鳴き声に悩んでいる飼い主さんも多いはず。
そんな時に効果的なのが、無視トレーニングです。
まずは子犬が鳴いても、無視を徹底しましょう。
反応してしまうと鳴き声が継続してしまうからです。
そして鳴き声が止んだ時に、しっかりと褒めることが大切です。
望ましい行動を積極的に評価していくことで、無駄吠えが減っていくのです。
もちろん一朝一夕ではなかなか効果は出ませんが、諦めずに時間をかけて根気強く続けることが重要です。
飼い主さんの粘り強さが 問題解決の鍵となるでしょう。
適切な運動
子犬は運動不足でストレスがたまりやすいものです。
そのストレスが無駄な鳴き声につながる可能性もあります。
そのため、適切な運動を心掛けることも重要なポイントです。
子犬の年齢や体力に合わせて、散歩や運動の時間を十分に確保しましょう。
家の中で思い切り遊ばせてエネルギーを発散させることも効果的です。
おもちゃなどで運動不足を解消できる環境を作ることをおすすめします。
参考:飼い犬を遊ばせる5つの方法とは?おもちゃを使って適度な運動をさせよう!#204
コミュニケーション
子犬との信頼関係を築き上げることも、鳴き声を減らすためには欠かせません。
そのためには、しっかりとコミュニケーションを取ることが何より大切です。
まずは効果的なコミュニケーションの一環として、子犬が好きな遊びを見つけて、一緒に思いっきり遊びましょう。
そしてこまめに名前を呼び掛けたり、愛情たっぷりなスキンシップを心掛けてあげてください。
このようにして信頼関係を深められば、子犬も飼い主さんの言うことをよく聞くようになり、無駄な鳴き声も減っていくはずです。
愛情を込めたコミュニケーションを大切にすることが、最も重要なポイントです。
子犬の鳴き声に対するしつけの注意点
子犬の鳴き声に対するしつけには、注意が必要です。
適切なしつけ方法を心がけなければ、かえって子犬に悪影響を及ぼしかねません。
子犬の月齢を考慮する
子犬の月齢によってしつけ方は異なります。
生後1~2ヶ月頃の子犬は環境になれることが最優先で、複雑なしつけは無理があります。
そのため、この時期は子犬になれ親しむことに専念しましょう。
一方で、生後3~4ヶ月を過ぎる頃からは本格的にしつけを始められます。
この時期に身につけた行動は、その後の子犬の成長に大きな影響を及ぼします。
生後7ヶ月以降は精神的にも落ち着きが出てくるので、より高度なしつけが可能になります。
このように、子犬の月齢に合わせて、しつけの内容や強度を調整していくことが肝心なのです。
報酬と罰(飴と鞭)のバランスを配慮する
しつけには「報酬」と「罰」の2つの方法があり、その使い分けが重要になります。
望ましい行動をした際には、おやつやおもちゃ、言葉掛けなどで積極的に「報酬」を与えましょう。
これが子犬の良い行動を育てる上で効果的です。
一方で、悪い行動には一時的に制止する程度の「罰」を与えるにとどめるべきです。
罰を与えすぎるとストレスが溜まり、逆効果になりかねません。
つまり、報酬と罰のバランスを上手く取ることで、適切なしつけが可能となるのです。
一貫性と根気が不可欠だと知っておく
しつけは一朝一夕にはできません。
飼い主自身の一貫した姿勢と根気強さが何より大切です。
例えばトイレのしつけなら、生活パターンを意識して毎日同じようにしつける必要があります。
一貫したしつけを続けることで、子犬は学習しやすくなります。
愛情を持って接する
しつけを行う際に何より重要なのは、子犬に愛情を持って接ることです。
厳しすぎるしつけは子犬を虐げてしまう可能性があります。
むしろ、愛情を込めて褒め伸ばす姿勢が大切です。
飼い主の愛情に包まれた中で、子犬は安心して成長し、良い習慣が身につくはずです。
また、愛情とともに適切なしつけを行えば、子犬との絆はより一層深まるでしょう。
しつけで解決できない鳴き声は要注意
子犬のしつけを頑張っても、なかなか鳴き声が収まらない場合があります。
そのようなケースは、病気のサインかもしれません。
子犬の鳴き声に注意を払い、異常があれば獣医師に相談することが大切です。
鳴き声が病気のサインかも
通常の鳴き声とは違う様子が見られる場合は、病気のサインである可能性があります。
突然の激しい鳴き声は、痛みや体調不良のサインかもしれません。
また、鼻声や嗄声、咳など、鳴き声自体が異常な場合もあります。
さらに、鳴き声の異常以外にも食欲不振や嘔吐、下痢などの症状も危険信号です。
このような兆候がある場合は、痛みを伴うケガや関節炎、歯周病、感染症や内臓疾患、ストレスによる神経疾患などが考えられます。
一見すると子犬の鳴き声は可愛らしいものですが、異常があればそれを見逃さないようにしましょう。
成長過程をのぞいて、鳴き声に変化がないかを日頃から観察しておくことが重要です。
動物病院での診察
鳴き声や体調の変化に気づいたら、迷わず動物病院で診察を受けましょう。
まずは獣医師による問診があり、鳴き声の症状や飼育環境について詳しく聞かれます。
次に身体検査で体温や脈拍、呼吸数などをチェックします。
その上で、必要に応じて血液検査やレントゲン検査、超音波検査などの検査が行われます。
これらの検査データから、具体的な病気の原因を特定していきます。
そして原因が特定されれば、薬物療法による治療や、場合によっては手術治療が必要になる可能性もあります。
ストレスが原因の場合は、行動療法も検討されます。
異常が見られる場合には、どのようなケースでも専門家のアドバイスを聞き、素直に実践することが重要です。
しつけと医療機関の連携
子犬の鳴き声に悩んでいる飼い主は、しつけと医療の両面からアプローチすることが肝心です。
まずは獣医師に相談し、適切なアドバイスを仰ぎましょう。
鳴き声の原因が病気であれば、その治療を優先する必要があります。
その上で、しつけの方法を獣医師の指導に基づいて改善していきます。
例えば、子犬の体調面に配慮したり、ストレスを軽減するような工夫をしたりします。
このように、獣医師の協力が必要な場合は、しつけと獣医療の両輪が必要になります。
子犬が鳴く原因を特定して、適切なしつけを行おう!
子犬の鳴き声は飼い主を悩ませる原因にもなりますが、その鳴き声には必ず何らかの理由や意味があります。
子犬はコミュニケーションの手段として鳴き声を上げているのです。
鳴き声の種類や出方から、子犬の気持ちを汲み取ることができます。
例えば「キャンキャン」という高らかな鳴き声は、遊びたい、構ってほしい、トイレに行きたい、空腹を訴えているサインかもしれません。
一方で「クゥン」という弱々しい鳴き声は、痛みや寂しさ、体調不良を表していることも。
このように鳴き声一つひとつに意味があり、状況によって変わってくるのです。
もちろん月齢によっても鳴き声は変化します。
生後1〜2ヶ月頃は母犬から離れた不安な鳴き声が多く、3〜4ヶ月頃になると活発になり遊びたい鳴き声が増え、5〜6ヶ月を過ぎるとコミュニケーションの鳴き声が目立つようになります。
鳴き声の理由や子犬の気持ちを理解できれば、適切なしつけが可能になります。
トイレトレーニングやクレートトレーニング、無視トレーニングなどが有効です。
さらに運動不足の解消や、愛情を込めたコミュニケーションも重要です。
一貫性と根気強さを持ってしつけを行う必要があります。
しかし、一方でしつけを頑張っても収まらない場合は要注意です。
子犬の異常な鳴き声は、痛みや病気のサインかもしれないためです。
突然の激しい鳴き声、異常な声の出方、それ以外の体調不良を伴う症状があれば、迷わず獣医師に相談しましょう。
動物病院で原因を特定し、治療とともにしつけ方法の改善を行うことで、鳴き声問題に根本的な解決が得られます。
これらのことから、子犬の鳴き声にはさまざまな背景が存在しています。
そのため、単なる鳴き声問題として認識するのではなく、その原因を特定して、それに適したしつけを行うことが重要です。
成犬になってからのしつけは難易度が上がるため、できるだけ早くに直してあげたいですね!
Q&A
Q1: 子犬が鳴いているときはどうしたらいい?
A1: 理由を確認し、単なる要求なら適切なしつけを。異常な鳴き声や体調不良の兆候があれば獣医に相談。
Q2: 子犬が4ヶ月で吠えるようになったのですが、どうしたらいい?
A2: この時期は活発になり吠えが増える。無視トレーニングや運動不足解消などのしつけが効果的。異常があれば獣医に相談。
Q3: 子犬が遊んでいたら吠えるのはなぜ?
A3: 構ってほしい、もっと遊びたいなどの要求の現れ。一緒に遊んだり褒めたりして愛情を持って接することが大切。
大切な家族である愛犬に良質なアイテムを!【IDOG&ICAT】
日々を一緒に過ごし、いつもあなたを癒してくれる愛犬は、れっきとした家族の一員です。
そんな愛犬の一生は、飼い主であるあなたと過ごす時間で決まります。
どうせなら楽しく、リラックスできる時間を長く作ってあげたいですよね。
また、あなたも愛犬の可愛い姿や、楽しんでいる姿をできるだけ多く見たくありませんか?
幸せな時間を創出する1つの手段が、飼い犬のために作られたグッズやアイテムです。
実はこれらのアイテムは、愛犬がリラックスできる時間を生み出すだけではなく、健康状態の改善にも大きく役立ちます。
ペットの幸福度を高めながら体のケアもできるなんて、一石二鳥ですよね!
もし、あなたの愛犬や飼い主さんが以下のように感じているのであれば、アイテムで解決できる可能性があります。
- 服を着せても嫌がってしまう
- 抜け毛が多くて悩んでいる
- ご飯を食べるときの体勢がしんどそう
このような場合、愛犬にとって着心地の良い「ドッグウェア」や、抜け毛に特化した「ブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが有効的です。
アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。
しかし、あなたの愛犬にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。
犬グッズを扱っている通販サイトは数多く存在しますが、せっかくならIDOG&ICATがオススメです。
IDOG&ICATは創業33年の縫製工場を母体とするペットグッズメーカーです。
縫製工場から派生した老舗メーカーだからこそ、品質にこだわった最高級の犬グッズをお客様に提供しています。
IDOG&ICATの大きな特徴は、ペットのことを第一優先に考えた商品づくりです。
愛犬が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。
あなたと愛犬がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?
人気記事ランキング
人気記事ランキング
希少種ミヌエットはどんな猫?性格や特徴、育て方のポイントも解説!
93294views
猫がふみふみする理由とふみふみしない猫との違いとは? #50
65052views
ベンガルキャットが持つ意外な性格とは?しつけは子猫のときから行おう! #115
55132views
アメリカンショートヘアはどんな性格?オスとメスの違いも徹底解説! #77
49540views
猫が急に走り出す7つの理由とは?走る猫の注意点とその対処法も解説! #82
48014views
飼い猫が脱走したらどうしたらいい?探し方と事前にできる対策とは? #48
43381views
ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
36666views
猫のロシアンブルーってどんな性格?「猫ではない」と言われるほどの忠誠心を持つ #129
36561views
