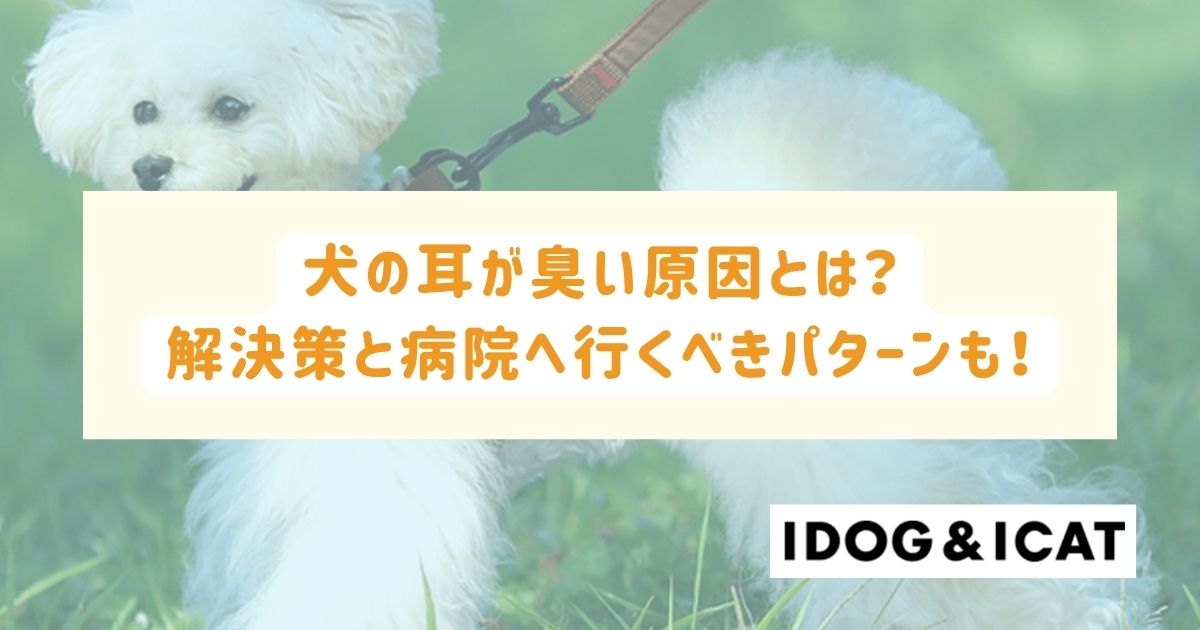
目次
犬の飼い主の方であれば、犬の健康に気を遣うことは当たり前のことでしょう。
しかし、意外に見落としがちな部分が「犬の耳」です。
犬の耳は、人間と同様に非常に重要な部位であり、炎症や感染症などの病気が発生すると、犬の健康を脅かすことがあります。
「最近、愛犬の耳が臭い…」と感じるのであれば、危険信号かもしれません。
- 愛犬の耳が臭いけど原因はなに?
- その対処法を知りたい!
- 犬の耳掃除は何回に一度行うべきなの?
本記事では、犬の耳が臭い原因や耳掃除の方法とその注意点を解説します。
そのため、上記のような悩みを抱えている人は、特に本記事を最後までご覧くださいね。
犬の耳が臭い原因
犬の耳が臭う原因は、様々なものが考えられます。
代表的な原因は、以下の通りです。
- 外耳炎
- 耳ダニ
- 中耳炎
- 腺臭症
- 食事の乱れ
外耳炎
外耳炎は、耳の中の細菌や真菌が増殖して引き起こされる病気で、犬の中でも最も一般的な病気の一つです。
外耳炎の症状には、耳の中が赤くなっている、耳垢が増える、痒がるなどがあります。
耳垢が増えることで、臭いの原因となることがあります。
外耳炎は犬種によっても注意が必要です。
それはダックスフンドやレトリーバー、シーズーなどの「垂れ耳」の特徴を持った犬種です。
また、プードルなどの外耳道に毛が生えている犬種も該当します。
これらの犬種は、その耳の特徴から通気性が悪く、外耳炎を発症しやすい傾向にあります。
耳ダニ
耳ダニは、犬の耳の中に寄生するダニのことです。
犬が寄生されることで、耳の中がかゆくなったり、臭いがする場合があります。
これは犬同士の接触や、草むらなどの外部環境からも感染します。
また、耳ダニが原因で「外耳炎」を発症するケースも見られます。
中耳炎
中耳炎は多くの場合、外耳炎が放置された場合に起こり得ます。
そもそも中耳炎は、通常外耳道から中耳に細菌やウイルスが侵入したことによって引き起こされるものです。
症状には、頭をかいたり、耳を引っ張ったり、頭を傾けたりすることが含まれます。
また、耳の中に膿がたまったり、耳から臭い液体が出たりすることもあります。
腺臭症
腺臭症は、脂質の分泌物によって発生する臭いのことです。
犬の場合は肛門腺からの分泌物によって引き起こされることがあります。
つまり、肛門腺からの分泌物が耳に付着することで、耳から臭いが発生しているケースです。
また腺臭症は、犬種によって異なる症状を引き起こすことがありますが、一般的には非常に臭いがきつく、犬の周りの空気に悪臭を放出します。
食事の乱れ
犬の食事が乱れていることも原因の1つです。
この場合、口臭や体臭、耳の臭いが発生することがあります。
例えば、食事の質や量に問題があると、犬の免疫力が低下し、細菌感染などが起こりやすくなります。
これにより、犬の耳の中に細菌が繁殖し、臭いの原因となるのです。
また、犬が食べ物を食べる際に、口の周りや耳の中に食べカスが付着することがあります。
これが残っていると、細菌の繁殖を促進し、耳の臭いの原因となり得ます。
これらのことから、犬の食事は栄養バランスが取れたものを選び、適切な量を与えるようにしましょう。
犬の耳が臭い!3つの予防策
犬の耳が臭くならないように、普段から以下のような予防策を行う必要があります。
- 定期的な耳掃除を行う
- 適切な食事を与える
- 犬の耳の形に合わせたケアをする
定期的な耳掃除を行う
1つ目の予防策は、定期的な耳掃除を行うことです。
耳掃除により耳の中の汚れや細菌を取り除くことで、耳の臭いを軽減する効果があります。
最初にやり方がわからない場合は、獣医師から指導を受けたり、慣れている人に教えてもらうようにしましょう。
また、耳掃除をするにあたって、専用のクリーナーを使うことが大切です。
適切な食事を与える
2つ目は、適切な食事を与えることです。
犬に適切な栄養素を与えることで、耳の臭いを軽減することができます。
特に、犬の健康に必要な栄養素を含むフードを選ぶことが重要です。
ライフステージごとのペットフードの選び方においては、下記サイトをご参考ください。
参考:一般社団法人ペットフード協会-ペットの食事について知ろう!–
犬の耳の形に合わせたケアをする
3つ目は、犬の耳の形に合わせたケアをすることです。
そもそも耳の形状は、犬種によって異なります。
そのため、犬の耳の形に合わせたケアを行うことが求められ、その適切なケアによって耳の臭いを軽減できます。
例えば、垂れ耳の犬は耳の中が湿気を持ちやすくなっているため、他の犬種と比較して、より一層耳の中を清潔に保つことが大切です。
病院へ連れて行くべき5つのケース
犬の耳に異常があり、以下のような症状が見られる場合には、病院へ連れて行くべきです。
- 耳が腫れている
- 耳から異臭がする
- 耳を痛がっている
- 耳に異物が詰まっている
- 耳から出血している
耳が腫れている
1つ目は、耳が腫れているケースです。
犬の耳が腫れている場合は、外耳炎や中耳炎、腫瘍などの可能性があるためです。
腫れがひどい場合は、痛みを伴うことがあります。
耳から異臭がする
2つ目は、耳から異臭がするケースです。
犬の耳から異臭がする場合は、これも外耳炎や中耳炎、耳ダニなどの病気が原因である可能性があります。
これ以上悪化させないためにも、早めに獣医師に相談するようにしましょう。
耳を痛がっている
3つ目は、耳を痛がっている場合です。
具体的には犬が耳を触られると痛がる、頭を傾けたり振ったりするなどの症状が現れます。
この場合も早めに獣医師に相談することが大切です。
耳に異物が詰まっている
4つ目は、耳に異物が詰まっているケースです。
異物が詰まっている場合は、自力で取り除くことができず、獣医師による処置が必要になります。
具体例は以下の通りです。
散歩に行って植物の葉や種子・虫などが混入するケースやシャンプーなどで水やお湯が大量に耳に入った場合を指します。
外耳道の異物の主な症状として耳を下に向ける仕草・首や頭を大きく振る動作を何度も繰り返します。
痒み等刺激が加われば、足で掻いたり突っ込んだりしますが、改善されずに何度も繰り返すのが特徴です。
引用元:動物病院ナビ&獣医師相談-犬の外耳道の異物の症状–
耳から出血している
最後は、耳から出血しているケースです。
出血している場合、多くの原因は外耳炎によるものです。
そのほか、耳の内部や外部に傷がある可能性も考えられます。
原因によって治療法が異なるため、早めに獣医師に相談して、適切な治療を受けるようにしましょう。
犬の耳掃除のやり方
犬の耳掃除は、犬の健康にとって非常に重要です。
定期的な耳掃除は、耳の中にたまった汚れや細菌を取り除き、耳の炎症を防ぐことができます。
しかし、間違った方法で行うと、犬に痛みを与えたり、逆に炎症を引き起こすことがあります。
ちなみに犬の耳には自浄作用があるため、基本的には目視できる範囲の汚れを優しく拭き取るだけでOKです。
無理に耳の奥の方まで掃除する必要はありません。
具体的なやり方は、以下の通りです。
- 耳に触っても嫌がらないようリラックスさせる
- 耳専用のクリーナーをコットンに染み込ませる
- 目視できる汚れを拭き取る
- 無事にできたら愛犬を褒めてあげる
コツはできるだけ短時間で終わらせ、ご褒美を与えることです。
このように行うことで、愛犬に「耳掃除は平気、ご褒美をもらえる嬉しいこと」と認識してもらえます。
犬の耳掃除の頻度
犬の耳掃除の頻度は、犬種や耳の形によって異なります。
一般的な目安は、月に1,2回程度です。
しかし、犬の耳の状態によっては、より頻繁に掃除する必要があります。
具体的には以下のケースです。
- 耳の臭いが強い
- 耳垢が多い
- 犬の耳の形が複雑
また、上記に限らず季節によっても犬の耳の状態は変わります。
夏場は、犬が水遊びをすることにより、耳の中に水がたまることがあります。
このため、夏場はより頻繁に耳掃除を行う必要があると言えます。
つまり、犬の耳掃除における頻度は、犬の健康状態や飼育環境を把握しながら、適切な間隔で行うことが大切です。
犬の耳掃除における注意点
犬の耳掃除を行う際には、以下のような注意点があります。
- 犬が痛がらないようにする
- 綿棒や人間用の耳かきは使わない
- 耳を擦らない
- 耳毛を抜かない
犬が痛がらないようにする
1つ目の注意点は、犬が痛がらないようにすることです。
当然のことですが、犬の耳は非常に敏感な部分であるため痛みを感じやすいことから、細心の注意を払う必要があります。
また、犬の耳の中を掃除する前に耳の中を確認し、もし異常がある場合は獣医師に相談しましょう。
綿棒や人間用の耳かきは使わない
2つ目は、綿棒や人間用の耳かきは使わないことです。
これらのアイテムを用いることで、犬の耳に損傷を与える恐れがあります。
犬の耳掃除を行う際には、コットンなどで耳の外側の汚れのみを取り除くようにしましょう。
ちなみに綿棒は柔らかい素材でできていますが、誤って汚れを奥に押し込んでしまったり、綿棒の一部が耳の中に残ってしまう危険があります。
耳を擦らない
3つ目は、耳を擦らないことです。
汚れを拭う際、擦って取り除いてあげたくなりますが、これはNGです。
耳はデリケートな部位であるため、傷つける恐れがあります。
耳毛を抜かない
最後は、耳毛を抜かないことです。
耳毛が多い犬種に関しては、通気性を良くしようとして、耳毛を抜いてしまう飼い主さんが稀に存在します。
しかし、耳毛は埃や汚れなどを防ぐ機能を持っているため、抜いてしまうはNGです。
耳毛を抜くことで、耳の病気になるリスクを高めてしまいます。
FAQ
犬の耳が臭い原因は何ですか?
犬の耳が臭い原因は、外耳炎や中耳炎、耳ダニなどがあります。
犬の耳が臭い場合、自分で治療することはできますか?
自分でできることとして、犬の耳掃除が治療・予防策として挙げられますが、症状がひどい場合は獣医師に相談することをおすすめします。
犬の耳の炎症を防ぐためには何ができますか?
犬の耳の炎症を防ぐためには、定期的な耳掃除や適切な食事、犬の耳の形に合わせたケアが重要です。
犬の耳掃除はどのくらいの頻度で行うべきですか?
犬の耳掃除は、犬種や耳の形によって異なりますが、一般的には月に1,2回程度が適切です。
犬の耳掃除における注意点は何ですか?
犬の耳掃除における注意点は、犬が痛がらないようにすることや綿棒や人間用の耳かきは使わないこと、耳を擦らないことなどが挙げられます。
犬の耳が臭わないように、普段からのケアを意識しよう!
犬の耳が臭い原因には、以下のことが考えられます。
- 外耳炎
- 耳ダニ
- 中耳炎
- 腺臭症
- 食事の乱れ
症状が発症する前に、普段から行うケアが重要です。
具体的には、以下の通り。
- 定期的な耳掃除を行う
- 適切な食事を与える
- 犬の耳の形に合わせたケアをする
もし何らかの症状が発症し、以下のケースが見られる場合には、早急に動物病院へ連れて行ってあげましょう。
- 耳が腫れている
- 耳から異臭がする
- 耳を痛がっている
- 耳に異物が詰まっている
- 耳から出血している
大切な家族の一員である愛犬が、末永く健康でいられるためにも、普段のケアを欠かさないようにしたいですね!
大切な家族である愛犬に良質なアイテムを!【IDOG&ICAT】
日々を一緒に過ごし、いつもあなたを癒してくれる愛犬は、れっきとした家族の一員です。
そんな愛犬の一生は、飼い主であるあなたと過ごす時間で決まります。
どうせなら楽しく、リラックスできる時間を長く作ってあげたいですよね。
また、あなたも愛犬の可愛い姿や、楽しんでいる姿をできるだけ多く見たくありませんか?
幸せな時間を創出する1つの手段が、飼い犬のために作られたグッズやアイテムです。
実はこれらのアイテムは、愛犬がリラックスできる時間を生み出すだけではなく、健康状態の改善にも大きく役立ちます。
ペットの幸福度を高めながら体のケアもできるなんて、一石二鳥ですよね!
もし、あなたの愛犬や飼い主さんが以下のように感じているのであれば、アイテムで解決できる可能性があります。
- 服を着せても嫌がってしまう
- 抜け毛が多くて悩んでいる
- ご飯を食べるときの体勢がしんどそう
このような場合、愛犬にとって着心地の良い「ドッグウェア」や、抜け毛に特化した「ブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが有効的です。
アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。
しかし、あなたの愛犬にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。
犬グッズを扱っている通販サイトは数多く存在しますが、せっかくならIDOG&ICATがオススメです。
IDOG&ICATは創業33年の縫製工場を母体とするペットグッズメーカーです。
縫製工場から派生した老舗メーカーだからこそ、品質にこだわった最高級の犬グッズをお客様に提供しています。
IDOG&ICATの大きな特徴は、ペットのことを第一優先に考えた商品づくりです。
愛犬が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。
あなたと愛犬がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?
人気記事ランキング
人気記事ランキング
希少種ミヌエットはどんな猫?性格や特徴、育て方のポイントも解説!
93294views
猫がふみふみする理由とふみふみしない猫との違いとは? #50
65052views
ベンガルキャットが持つ意外な性格とは?しつけは子猫のときから行おう! #115
55132views
アメリカンショートヘアはどんな性格?オスとメスの違いも徹底解説! #77
49540views
猫が急に走り出す7つの理由とは?走る猫の注意点とその対処法も解説! #82
48014views
飼い猫が脱走したらどうしたらいい?探し方と事前にできる対策とは? #48
43381views
ラグドールの性格や特徴とは?子猫のときから愛嬌あり!飼育時には注意点も #111
36666views
猫のロシアンブルーってどんな性格?「猫ではない」と言われるほどの忠誠心を持つ #129
36561views
